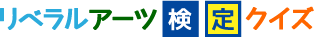夏休みのお知らせ(ことば文化特設サイト)
ことば文化に関する気になるトピックを短期連載で紹介していきます。
-
- 2024年12月03日 『林真衣(東京大学大学院人文社会系研究科博士課程)『言語学者のニューカレドニア: メラネシア先住民と暮らして』(大角翠/著)』
-
「autumn 秋の書評祭り」第7回を担当する林真衣 (はやし・まい) です。私は東京大学大学院に所属しており、フィリピンで話されているタガログ語とイロカノ語を研究しています。研究するにあたっては、日本在住の話者の方にご協力いただいて調査することもあれば、フィリピンに滞在して調査をすることもあります。
今回紹介する本は、2018年に出版された『言語学者のニューカレドニア: メラネシア先住民と暮らして』です。著者はニューカレドニアの少数言語を中心に研究されている大角翠 (おおすみ・みどり) 先生です。本書は大角先生がニューカレドニアで行った言語調査の日々を綴ったエッセイです。舞台となるニューカレドニアは、太平洋のメラネシアという地域にあります。合計すると日本の四国ほどの面積になるニューカレドニアの島々では、28もの先住民の言語が話されています (p.12)。
私がこの本を手に取ったのは、大角先生が研究されているニューカレドニアの言語と私が研究しているフィリピンの言語に共通点があり興味を惹かれたからです。ニューカレドニアもフィリピンも島々で多くの言語が話されており、それらの言語の多くは世界最大級の言語群と言われるオーストロネシア語族に属しています。実際に読んでみても、フィリピンの情景を思い浮かべながら太平洋に位置する島国での調査に思いを馳せることができる点は、私にとってお気に入りポイントの1つです。
本書で主に取り上げられている言語は、ニューカレドニアの先住民の言語のうち2つ、ティンリン語とネク語です。話者数はそれぞれティンリン語が260人、ネク語が200人ほどだそうです。ティンリン語とネク語は近くで話されている言語ですが、相互に理解することはできません。日本語のようないわゆる大言語に囲まれて生きていると、話者数百人の言語が点在する環境は想像がつきづらいかもしれません。
ですが、世界を見渡すと話者の少ない言語は決して珍しくありません。世界的な少数言語の研究団体 SIL が公開している Lewis et al. (2015: 8) によると、フィリピンには182の言語があり、そのうち10.4%にあたる19の言語は第一言語として用いる話者が1,000人よりも少ないと報告されています (182言語にはオーストロネシア語族以外の言語が含まれており、19言語にはすでに話者が0人であるなどの理由で話者数の統計をとっていない言語が含まれています)。
現在世界では6,000から7,000の言語が話されていると言われています。その中には、話者が少なく消滅の危機に瀕している言語が数多くあります。驚くべきことに、世界の50%もの言語が今世紀中に消滅するとの予測もあります (Crystal 2000)。このような消滅の危機に瀕している言語は「危機言語」と呼ばれています。本書で取り上げられるティンリン語とネク語はまさしく危機言語と言えます。
言語が消滅するということは何を意味するのでしょうか? 本書に登場するティンリン語の調査に協力した話者は、自分たちの言語が使われなくなってきていることと同時に伝統的な習慣が守られなくなっていることに危機感を感じていていたそうです。言語が消滅するということは、単に言語が消えることではなく「その言語にだけ存在していた稀有な世界観や認知体系、叡智と繊細な感情のひだが永遠に失われるということ」(p.278) を意味しています。
では、多くの言語が消滅の危機に瀕している現代社会で言語学者は何ができるのでしょうか?言語学者にできること、それは「言語に凝縮された独特な世界観、認知・意味体系、音や文法、他の言語にはない不思議な言語現象について調査し、書き残すこと」(p.275) と言えます。このことは、言語の消滅危機という差し迫った課題に対して大変意義のあることです。
本書では、大角先生が言語学者としての役割を実践されている姿を垣間見ることができます。「私は同じものを食べ、働き、できる限り考え方、感じ方でも彼らに近づきたいと思っていた。そうでなければ彼らの言語を理解することは無理だろうと。」(p.110) このような強い信念のもと、知らない世界に一人で飛びこみ、大角先生は生きている言語を、世界観を書き留めていくのです。
ここからは本書の構成を紹介したいと思います。全体は調査準備編、ティンリン語調査編、ネク語調査編に大きく分けられます。第1章と第2章が調査準備編です。オーストラリアの大学院で学んでいた大角先生は、教授たちの助言を受けてニューカレドニア行きを決断します。ニューカレドニアに着いて「天国にいちばん近い島」を訪れたり、ゆったりしすぎた時間感覚に振り回されたりしながら、なんとかティンリン語の調査地にたどりつきます。
第3章から第9章までがティンリン語調査編です。ティンリン語を教えてくれるおじいさんヌーヌーと出会い、調査を開始します。時には朝から晩までヌーヌーと生活を共にし、調査地から遠く離れたティンリン語話者に会いにいく旅にもヌーヌーと一緒に出かけます。ここでは大角先生とヌーヌーの関係性にも注目して読んでいただきたいです。
本書では言語が持つ特徴も分かりやすく説明されています。例えば、ティンリン語の所有構造は複雑です。身体部位のように所有物と所有者を切り離すことのできない所有のことを、専門的には「分離不可能所有」と呼びます。分離不可能所有の場合、必ず所有者を付けて所有物を言う必要があります (単に「頭」とは言えず常に「私の頭」「彼の頭」と言う)。一方、分離可能所有もあり所有している目的によって (同じココナッツでも食べる?飲む?植える?) 所有物の言い方が異なります。本書はこのような言語現象に着目して読んでも楽しむことができます。
第10章から第12章までがネク語調査編です。時にはいも虫のごちそうをいただきながら、ネク語の調査を進めていきます。興味深いことに、ネク語の基礎的な単語や使う音の体系は隣のティンリン語と大きく異なることが明らかになります。最後にティンリン語やネク語をはじめとするニューカレドニアの先住民の言語の将来を見据え、本文を結んでいます。
私がこの本をおすすめする大きな理由は、大角先生がニューカレドニアと関わった30年もの歳月が1冊に凝縮されていて読み物として大変面白いからです。大角先生が経験された出来事一つ一つに驚いたり、出来事に添えられた大角先生の正直な心の声にくすっと笑ったりしながら読み進めることができます。慣れない土地で話者数百人の言語をいかに一から調査していくか、想像が掻きたてられます。言語学に携わる方にはもちろんのこと、この書評を読んでなんとなく興味を持たれた方にも、ぜひ読んでいただきたい1冊です。
最後に、書評らしくこの本唯一の注意点を述べておきます。大角先生を取り巻くニューカレドニアの人々を丁寧に描いているからこそ、本文中にはかなり多くの人物が登場します。そのため、のんびり読んでいると「○○って誰だったっけ?」となりがちです。これから読まれる方は家族構成への意識を高めながら、可能であれば家系図をメモしながら、ニューカレドニアの少数言語の世界に入りこんでみてください。
最終回となる次回12月17日は、松田俊介氏が『言語学の教室: 哲学者と学ぶ認知言語学』を紹介します。どうぞご期待ください。
書誌情報
大角翠 (2018) 『言語学者のニューカレドニア: メラネシア先住民と暮らして』 東京: 大修館書店. https://www.taishukan.co.jp/book/b375332.html
Crystal, David. 2000. Language Death. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
Lewis, M Paul, Gary F. Simons, & Charles D. Fennig. 2015. Ethnologue: Languages of Philippines. 18th edn. Dallas: SIL International.