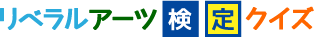言語のダイバーシティ(ことば文化特設サイト)
ことば文化に関する気になるトピックを短期連載で紹介していきます。
-
- 2021年06月22日 『言語のダイバーシティ 12. 翻訳 仁科陽江(広島大学)』
-
12. 翻訳
「バベルの塔」を建てようと企てたとき、人間は皆同じことばを話していたという。天にも届くというこの塔の建設が神の怒りに触れ、その実現を阻むために、神は人々に異なる言語を与えた。ことばが通じず、意思疎通ができなくなった無力な人間たちは、各地に分散していった。旧約聖書の創世記の記述である。
現代の我々にとって、異なる言語間の理解のためには翻訳は必須である。しかしながら、言語が異なるのであるから、翻訳に限界があるのも当然だ。
翻訳は裏切りだ、とも言われる。美しい訳文にしようとすると意訳になって、そこでは原文らしさを失ってしまったり、原文に忠実に訳そうとすれば、できあがった訳文がぎくしゃくしてしまったりする。そのようなジレンマを「不実な美女か貞淑な醜女(ブス)か」と、ロシア語同時通訳者、米原万里氏が表現したのは言い得て妙である。私自身、ドイツで通訳(の真似事)のアルバイトをして学費を賄っていた頃を振り返れば、必要に応じてこの二種類の女を演じ分けて訳していた気がする。(この表現がどうして男でなくて女の喩えになっているのかについては、米原1998にあるように、ヨーロッパで古くから言われている格言にあるらしい。)
川端康成がノーベル文学賞を受賞したときに、翻訳者のおかげだから賞の半分は翻訳者のものだ、と言ったのは有名な話である。川端作品を英訳したサイデンステッカーは、日本の古典や現代文学、日本社会に精通しており、彼の英訳は欧米人の琴線にも触れたのであろう。
以下の例は『雪国』(Snow Country)の冒頭部分である。日本語と英語の構造の違いが興味深い。
国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。
The train came out of the long tunnel into the snow country. The earth lay white under the night sky. The train pulled up at a signal stop.
日本語の最初の一文「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」について、ドイツ人日本語学習者と日本語母語話者に、絵を描いてもらったことがある。すると、ドイツ人日本語学習者の絵はどれも、トンネルから出てくる汽車が描かれている。それに対して日本人の描いた絵は、窓から見える雪国の風景なのであった。
日本語の原文には「汽車」という言葉は書かれていない。3つ目の文で初めて汽車が登場する。そもそも日本語の文には「トンネルを抜ける」に対する主語がない。
主語が必須の英語に訳出する際、おそらく訳者は、汽車がトンネルから出てくる映像を、ドイツ人学習者のように難なく想像したのだろう。汽車が長いトンネルを抜けて雪国に出た、と、自然な英語で簡潔に能動的に表現した。英語やドイツ語の話者は、いわば外から俯瞰した見方をしている。
それに対して日本語話者は、主体を表す主語などなくてもよくて、電車の中にいる主人公に同化して、その視点から絵を描いた。
二つ目の文、「夜の底が白くなった」といういかにも文学的表現は、国語の時間ならばきっと、これはどういうことでしょう、と、先生が発問するところだ。これを英語に直訳したところでますますわからないだろう。むしろ、earth「大地」やsky「空」を補って、明快で具体的に描写したほうがずっと英語らしい。
学校の教科は国語と英語と分かれているが、こういう材料は教科を融合した授業形態に適している。優れた英訳と並べることによって、自国の文学の理解がより深まり、解釈がより広がり、同時に、英語らしさも見えてくるのではないだろうか。
文学にはどの言語圏にも愛好者がいる。ドイツのテレビ番組das literarische Quartett「文学カルテット」は四人で開催する書評会で、1988年から放映が続いている。2000年6月30日に村上春樹の「国境の南、太陽の西」が扱われたとき、評者間の見解の対立がもとで、長年のレギュラーが辞めたことがあった。そこでは翻訳であることを断りつつも、性描写など、言葉の問題も指摘された。「〜さん」がフォーマルで変だという的外れな指摘もあったが、そしてそれは即座に反論されたが、論争は、文学における恋愛の扱いの評価が個人の偏見として攻撃されるまでになってしまって、本質は見えないままで終わった感がある。
この放送を見たドイツの友人たちはこぞってこの小説を読み、筆者に意見を求めたが、彼らが問題とする焦点がずれているような気がしてならなかった。ドイツ語版のタイトルがGefährliche Geliebte「危険な愛人」となっていることも違和感がある。このドイツ語版は英語版からの重訳であり、結局翻訳の問題だったのかとある出版社の人は話していた。村上文学は世界中で人気があり、村上自身が英語の翻訳を手掛けることもあってか、彼の文体は翻訳しやすいとも言われている。それでも越えられない言葉の壁はやはり存在するのだろうか。
また、イタリアのパヴィア大学で研究滞在をしていたとき、暇にまかせて(?)ナタリア・ギンズブルグのCaro Michele「親愛なるミケーレ」というイタリア語の小説を原書で読んでいた。ドイツに戻ってから、ドイツ語訳を読んでみると、なぜか全く印象が違うのである。ミケーレをめぐるさまざまな人間像が違って見えて、これは翻訳のせいなのか、それともドイツ語に対する私の感覚なのか、うまく説明はできないのだけれど、言語の違いをそんなところでも痛感した経験だった。
筆者の思い出話になってしまったが、折々に感じた違和感を、いつかじっくりと検証したいと思っている。殊に文学作品においては翻訳がその理解のために重要であることは自明である。
翻訳は、対照言語学や比較文学などの分野とも密接に関連し、言語学と文学をつなぐ学際的研究の可能性を孕んでいる。
連載第10回で紹介したフランツ・カフカの小説を和訳したテクストでは、主語や目的語となる人称代名詞がドイツ語では必須であるのに対し、日本語では省略する方が自然であった。
では、日本語ではいつもそうやって省略するのかというと、グリム童話の日本語訳では、省略も代名詞も非常に少なくて、「王子様」や「お姫様」を何度も繰り返すのである。ドイツ語では両方のテクストで同様に人称代名詞が用いられている。同じ文学作品であっても、ジャンルによって、そのスタイルが異なり、日本語の場合は人称の使い方にその違いが如実に現れている。
人称の表現の仕方が日独で大きく異なるのは、新聞等のジャーナリズムの文章に見られる。ドイツ語では、同じ人を指す異なる描写が代名詞の代わりに交替することがある。「メルケル首相」が別の文では「ドイツキリスト教民主同盟の政治家」「東独出身の66歳」など、新たな情報がそのまま人称詞になる。日本語にはない書き方であるが、メルケルについて知っていれば、まだ理解できないことはない。
次のようなスポーツ新聞の記事ではどうだろう。
「負傷したマリオ・ゲッツェはマドリッドの試合開始後14分でベンチ入りした。マリオ・ゲッツェにとっては当分休みだ。ボルシア・ドルトムントのスターは左足の腿の筋断裂で数週間は欠場する。20歳の元ナショナルチーム選手は、今週土曜日の対FCバイエルン・ミュンヘンとなるブンデスリーガに出場しない。」
この和訳を日本人に読ませたところ、何人のことを書いてるの?と尋ねられたが、すべてマリオ・ゲッツェ一人のことである。学会発表中に日本人参加者に手をあげてもらったら、ほとんどが複数人と解釈していた。
このように、人称詞だけを取り上げても、テクストの比較が可能になり、そのスタイルの違いが明らかになる。そのまま日本語に訳したのでは意味が通じなくなるスタイルでもあることがわかる。
翻訳については翻訳の活動や実践の立場から語られることが多く、翻訳家の養成は、我が国ではほとんどが民間の機関や個人の精進に負っている。大学の研究室としては一部の個別言語・文学研究者によって翻訳研究translation studiesがなされてきたのが実情だろう。
ドイツでは、高等教育機関で通訳・翻訳の専門家を育成する伝統があり、現在約20の大学で、翻訳や通訳を専攻できる。ハンブルク、マクデブルク、ランツフーツでは手話通訳も専攻できる。
約20の中には、かつてのFachhochschule (University of Applied Sciences)と呼ばれた単科大学も含まれる。そこでは、技術的な応用科学や教員養成など、職業教育を志向し、翻訳・通訳専攻の場合は、修了時にディプロマが付与された。総合大学Universitätとの区別は、2000年前後から始まったボローニャ改革によって、なくなりつつあり、EU内の画一的カリキュラムに沿って、学士号や国家資格の取得が可能である。
筆者自身はボン大学大学院のSprach- und Übersetzungswissenschaft 言語学・翻訳学専攻の主任教授として仕事をした時期があり、言語学や翻訳理論の講義・演習の他、翻訳家養成の一環で、まだ公開前の映画データに字幕をつけるという実践を授業でやったこともあった。
言語研究の一環として翻訳学translatologyを考える場合、言語の基礎研究が、その記述や理論づけなどに関わる一般言語学にあるのに対して、翻訳への応用を支える理論的基盤となる応用言語学の一分野として位置付けられる。
応用言語学は、言語習得、翻訳、そして、前世紀半ば頃から、言語情報を処理するコンピューター言語学として、翻訳の機械化も目指された。また、最近では非専門的通訳・翻訳の実態も研究され、異文化やコミュニケーションの観点から広い意味で翻訳の意義が問われている。
筆者の留学先の一つであったハイデルベルク大学には、言語学科で一般言語学と比較言語学の専攻、それとは別に通訳・翻訳家養成のための学科があり、後者では、翻訳理論で有名なHans Vermeer教授が教鞭をとっていた。
言語学科のRobert Schmitt-Brandt教授は印欧語学者でありながら、言語研究者としてのレパートリーを広げるという意味もあってか、印欧語以外にも多く言語研究を行っていた。退官してから習得した言語はいくつもあって、学習者として謙虚に言語を学ぶ姿勢を生涯貫いた。数多くの言語文化圏出身の人との交流にも絶えなかった。
Klaus Heger 教授は、それと対照的に、筆者から見れば抽象の極みとも言える一般言語学理論を構築し、それを突き詰めたところでは、言語を経験的に知る必要はなくなったと、個別言語の研究をやめたという。しかし、授業では自身で独自に体系づけた言語の系統づけlanguage classificationに従って、学期毎にそれぞれ系統の言語の構造を扱い、学生たちは毎学期ある系統の言語について学び、発表もしていた。
この三人は皆、ハイデルベルク時代の筆者の恩師でもあるが、この三人のもとでならば、バベルの塔の建設は進んだかもしれない、などと、ふと思わせたりする人たちだった。
一般言語学・言語類型論の研究では、いわば世界のあらゆる言語を研究対象とする。未知の言語でも、その構造がわかるように、詳細な形態素解析を行い、最小単位の意味や文法機能を表すグロスをつける。このグロスについては、筆者の知る限りでは70年代のドイツでその方法論が模索され、それぞれの言語文化圏でバラバラに単語の逐語訳のように添えられていたものの体系化が試みられていった。
そのような言語研究では、むしろ、翻訳を見てはいけない。翻訳は便宜上添えるものに過ぎない。グロスがしっかりしていれば、その言語自体の独自の構造を理解して意味はわかるので、翻訳は自分の中でそれなりにしておけばよいだけなのである。
この連載では英語に常に日本語訳をつけたわけでなかったが、昔の言語学の文献では、英語、ドイツ語、フランス語の例に、グロスも翻訳もついていなかった。国際学会の公用語が、英・独・仏・伊・西の五か国語ということもよくあった。ヨーロッパ中心主義だとは言われても、当時は皆、外国語に堪能だったので、事実上はそれでまわっていて、通訳は不要だった。
筆者も直に体験したが、発表者がドイツ語で発表し、質問がフランス語で出たらフランス語で答え、あるいは英語で答えても、質問者は理解していた、など、その状況に応じて複数の言語が自由闊達に往来しているのだった。
欧州評議会が提唱する複言語主義plurilingualismは、個人の多言語運用を尊重する。それにはヨーロッパの学術的な歴史的背景があり、また、人の往来の中で、複数の言語環境にある人々の生活を保障するためにも、必然の考え方であったのだと思う。
現代のバベルの塔は、人々が理解できないようにするためにあるのでなく、人々が言語の多様性を知り、複数の言語の中で生きていくことを自覚するためにこそ存在するべきものである。
-
- 2021年06月15日 『言語のダイバーシティ 11. 言語表現と言語行動 仁科陽江(広島大学)』
-
11. 言語表現と言語行動
フランスの老舗出版社Assimilは、外国語教材のシリーズの一環で、Le Japonais sans Peineという日本語教科書を出している。媒介語としてはフランス語に限らず、現在、ヨーロッパ言語を中心にアラビア語やトルコ語を含む13の言語で書かれたものが公刊されている。
このフランス語のタイトルは、直訳すると、「痛みのない日本語」となり、各国語で出されているタイトルを見ても、英語版がJapanese with ease、ドイツ語がJapanisch ohne Mühe(苦労のない日本語)、イタリア語がIl Giapponese senza sforzo(努力なしの日本語)などとなっている。
日本語クラスの受講者が一度、こんなパラドックスはない、とつぶやいて、皆で大笑いしたことがある。(厳密に言えば、逆説というより、撞着語法oxymoronという、修飾される名詞の属性にそぐわない修飾句を用いる修辞表現に相当する。痛みも苦労も努力もなしに、難しい日本語が学べるはずがないという前提を、皆が共有しているので笑えるわけだ。)
独自のメソッドを適用したこの出版社の教材は人気があった。初心者向けの会話の導入部分としては、大抵の日本語教科書に「お元気ですか」とあるが、この本では「お変わりありませんか」とある。
こういう挨拶では、英語でWhat’s upとかWhat’s new、フランス語でQuoi de neuf、 ドイツ語でWas gibt’s Neuesや若者言葉でWas geht abなどなど、一連の表現があるが、これらは皆、「何か新しいことが起こったかどうか」を問うものである。
それに対して、日本語の表現を見ると、「何も変わらないかどうか」を確かめる表現になっている。もちろん、引っ越しや結婚など、近況の変化があれば相手は答えてくれるだろうけれども、この表現には、何も悪いことが起こらず、無事平穏に暮らせていますか、と安否を問う気持ちが含まれているのではないだろうか。変わらないことが良いことと考えられているのか、とヨーロッパの人たちは首を傾げ、また、そのようなものの見方にちょっとした感動を覚えるのだった。
挨拶や決まり文句など、言語の系統を同じくする言語間では、並行して似たような表現をすることが多い。印欧語では、その言語でどういうのかを調べずとも、ある別の印欧語から直訳してみたら、たいてい間違っていないことが多かった。それが日本語では全く異なる表現であることが多々ある。「お先にどうぞ」は英語でafter you、ドイツ語でnach Ihnen、フランス語でaprès vousなど、「相手が先」でなく、「自分が後」という表現をする。同じことを言うのだけれども、発想が真逆なのだ。
「こんにちは」に相当するのは、英・独・仏・伊・西・葡・ポーランド語・チェコ語などのヨーロッパ言語では、good day, guten Tag, bonjour (< bon jour), buon giorno, buenos dias, bom dia, dzień dobry, dobrý denと、すべて「良い」と「日」という二つの語彙で形成されている。ドイツ語、ポーランド語、チェコ語では「日」を表す語が対格なので、「良い日を(祈る)」など、「良い日」を目的語とする文の一部が省略されていることがわかる。それに対して日本語では、「今日は(良い日です)」とでも補うとすれば、省略部分が、日本語と上記のヨーロッパ語では逆である。
このような挨拶語は世界で様々な様相を見せる。(下記の例で固有の文字が用いられている語についてはローマ字化したものを載せている。)
「ありがとう」と感謝を述べるのに、「感謝する」という動詞の1人称単数形で表現するのがドイツ語danke、ポーランド語dziękuję、チェコ語děkuji、ペルシャ語motashakkeramなどで、それが「感謝」という名詞と「する」という動詞の組み合わせなのが、朝鮮語kamsa hamnidaやトルコ語teşekkür ederimなどである。
インドネシア語ではterima「受け取る」とkasih「愛情」で「愛情をうけとってください」、ビルマ語(ミャンマー語)では、kyayzuu 「恩を」+tinpartal「積む」、カンボジア語(クメール語)は、ar「喜ぶ」+koun「恩」、ラオス語は、khob「応える」+chai「心」など、様々に表現する。
また、多くの言語において外来語として用いられているフランス語のmerciは「慈悲」を意味し、イタリア語grazieやスペイン語のgraciasはラテン語のgratia「善意」のそれぞれ単数・複数形に由来する。フィリピン語(タガロク語)のsalamatはアラビア語に由来して「健康」を意味し、ウズベク語rahmatでは「思いやり」を意味する。
「ありがとう」と響きが似ているとよく言われるポルトガル語obrigado/aは「義務づける」の過去分詞形で男女の性差の標示がある。
「義務付けられる」という表現はドイツ語でも感謝の意味になるように、それぞれの言語はいくつか他の表現も持つ。朝鮮語のように丁寧さの度合いの違いもあろうし、また、こういう独立した語は外来語としても使われやすい。
そんな中、日本語の「ありがとう」が「有難し」、つまり存在し難い、というような意味から派生して、連用形「ありがたく」が音便化して独立した形式となったのは、ユニークだ。
挨拶語や決まり文句に宗教が反映されていることも多い。
仏・西・伊語の別れの挨拶adieu, addio, adios「さようなら」は、いずれも向格を表す前置詞a+「神」の形式であり、ドイツ語方言でもadeと借用されている。トルコ語の、立ち去る側が行う挨拶allahaısmarladıkは、イスラム教の神「アラー」と動詞ısmarlamak「命ずる」の組み合わせである。
ドイツ語のum Gottes willen「神の思し召しのために」は「お願いだから」「とんでもない」という意味に、leider Gottes「神の苦しみ」は「残念ながら」という意味に慣用句化している。
ある言語共同体をめぐる文化や歴史は、こんな形でも言語表現の中に見出されるのである。
これまでの連載で、言語のダイバーシティと題して、言語の多様な構造的特徴を示してきた。今回のような、日常のコミュニケーションに使われる言語表現も、それぞれの言語文化によって多様である。
ただし、それがどのように使われるか、という点では、辞書や文法書に詳しい記載があるわけでもなく、あまり知られていないのが実情だ。
日本語学習者が日本語の知識を得て正しい日本語を使用することができても、ある状況においての適切な表現、その文化に見合った言語行動ができないと、実際のコミュニケーションでは誤解やすれ違いを生むことだろう。それが母語での言語行動様式や習慣に則っているのであれば、それもまたある種の母語干渉である。
例えば誘いの場面で、試験前の忙しい時に遊びに誘うなど、誘われる側にとって負担度が高い場合にはいきなり用件に入るようなことを日本語母語話者はしないが、中国人学習者には、負担度の高低に関わらずそのような配慮が見られないという研究結果がある(李2020)。
勧誘表現として「〜しませんか」という表現を教科書で覚えたとしても、適切な言語行動のためには十分でない。依頼、謝罪、感謝などの場面でも、日本語母語話者には典型的な談話構造があり、学習者のそれとは異なっていることが少しずつわかってきている。
そのような知見を、異文化コミュニケーション能力として教育に取り入れるべく、日本語教育では、近年、言語行動の対照研究も行われている。
日本人の我々が外国語を使うときも同様である。たとえば欧米の人は過去の出来事に対して重ねて感謝することはない。私たちが日々よく使う「先日はありがとうございました」のようなお礼のし方も、Thank you for the other dayなどと言ったとしたら、なんのことかと怪訝そうな顔で見られるのが落ちだ。その出来事の時点ですでに感謝の言葉は聞いているのに、今重ねて言うのは何か企んでるのか、と勘繰られたりさえするかもしれない。
逆に未来に対する感謝についても、感覚が異なる。
ヨーロッパを旅行すると、何かを注意・要請する張り紙にはThank you / Danke / Merci / Grazieなど、最後に感謝の言葉があるだろう。この箇所に日本語で「ありがとうございます」は入らない。
早々に感謝されるとおしつけがましい感もあり、未来に向かった「よろしくお願いします」でさえ、まだこちらが承諾しているわけではないのに、というタイミングで、学習者から発せられることがある。
東日本大震災のニュースはドイツでも連日大きく取り上げられて、おばあさんがヘリコプターで救出された時に、消防士に向かって「すみません」と言ったシーンを、ドイツのアナウンサーはおばあさんがお詫びをしていると報道していた。ドイツ語ならば、感謝は示しても、天災は自分の落ち度ではないのだからお詫びの言葉は決して出ないだろう。日本語の「すみません」は感謝の表現に他ならないのだけれども、その心理には、相手に手間をかけてしまって申し訳ない、という思いもあるのであろう。ことばの意味と発話時の状況を繋ぐマッピングのされ方が、言語によって異なっているといえる。
言語間の違いはいろいろなところに現れる。
複雑と言われる日本語の待遇表現には、自分と自分に属するものや人をわざわざ貶めることで相手に敬意を表すという原理がある。出されたお茶が「粗茶」、自分の妻は「愚妻」であるなど、欧米の人たちにとってはほとんど人権蹂躙、理解のためにはかなりの想像力を必要とする。
Hungryという形容詞ひとつで空腹状態を表せる人たちには、「お腹がすきました」My stomach has become emptyのような奇妙な表現をわざわざ完了形で表現する、というのが、すでに驚きである。冒頭の「お変わりありませんか」でも見たように、日常の習慣化した表現ほど、そのような構造上の違いを孕んでいることが多い。
日本語学習者の学習動機はいろいろあろうけれども、言語自体に興味があるという人は、このような違いを面白がっている人が多いのかもしれない。手っ取り早く外国語の習得を狙うならば、同系統の似た類型を持つ言語を選べばいいようなものたが、敢えて、「難しい」と言われる日本語を選んだ人たちは、その「難しさ」にこそ面白さを見出して学習が続いているのではないだろうか。自分を貶めて相手に敬意を表したり、感謝のために相手にお詫びしたりするというそのメンタリティも彼らには未知のことであり、興味を引かれる。
言語自体には難しいとか易しいとかの区別はない。難しいというのは、学習者の母語からの距離が大きいということが要因のひとつであろう。言語類型として距離があればあるほど、異なっていればいるほど、学ぶべき文法項目が多くなる。文化的な距離もまた、言語行動や談話のスタイルの点から学習すべきことが多くなる。
しかし、そんなところにこそ、個別言語の表現上の違いを超えた、言語に共通する原理も見えてくるチャンスがあると考えたい。
言語を抽象化して考えようとするならば、ドイツ語を母語とする者であれば、英語やオランダ語よりも、日本語や、どこかの先住民の言語に親しんでみればいい。そして、異質のものに対して柔軟に想像力を広げてほしい。
それは日本人も同じだ。
外国語習得が英語一辺倒になってしまった感がある昨今だが、世界の多様な言語の一つ一つに普遍的に興味深い現象があり、日常の表現を支える文化があり、そのような言語を通して、私たちは自分の母語や言語生活に対する気づきも得ることだろう。
多様性を重んじる共生社会を形成する精神を育てるためにも、まずは一つ、知らない言語に親しんでみることから始めてみるのもいいのではないか。
-
- 2021年06月08日 『言語のダイバーシティ 10. 省略と指示 仁科陽江(広島大学)』
-
10. 省略と指示
日本語には省略が多いとよく言われる。
日本語学習者からは、日本語には省略が多いので、誰のことを指しているのかわからない、と言われることもある。
確かに日本語では、英語やドイツ語とちがって、誰が、誰に、誰の・・・などをいちいち言わないことが多い。
しかしながら、日本語母語話者は、それで誰のことがわからないから意味が通じないとかいうこともなく、支障なくコミュニケーションしているのだ。むしろ、学習者が何か言おうとするときにいつも「ワタシハ・・・」と発話を始めることの方が、私から見れば異様だ。ドイツ人学習者がそう言うときは、ドイツ語に置き換えてみるとたいてい1人称主語の文になるので、これは明らかに母語干渉で、話者がドイツ語で考えて日本語を話そうとしていることがわかる。
省略ということ自体は、多かれ少なかれどの言語にもあるだろう。言わなくてもわかることを重ねていう必要はないし、代名詞の使用などは、何度も同じ言葉を繰り返すことを避けることにもなる。ただし、そこでの文法的な制約は言語によって異なる。
省略が多すぎたり、論理が破綻していたり、結束性がなかったりして、話が通じないというのは、どんな言語の話者でもあり得ることで、これは言語によるのではなく話者によることなので論外。
「省略」というと、本来あるべきものが省かれて、あるいは略されて、無くなっている、という意味合いがある。しかし、「省略」をしなければならない場合があるとすれば、これはれっきとした文法事項である。
He washed his handsという英文を直訳すると、「彼は彼の手を洗った」となる。学校の英文解釈で所有格をきっちり訳し、このような文を作った読者諸氏はいないだろうか。日本語では、「彼は手を洗った」と「手」の所有者をことさら言わないことによって、動作主と指示対象が一致していることを表す。そうでなければむしろ誤解を生む。「夫は彼の手を洗った時など彼の濡れた手を私の服で拭く」と聞いて、誰の手?子供の手を洗ってやっているのか?と思ってしまうのは筆者だけでないだろう。
ここでお笑いネタをひとつ。
コロナ禍の昨今、イベント会場では感染予防を徹底している。会場入り口で消毒液を持って立って、「会場に入る前に手を消毒してください」と声をかけているスタッフに、消毒液でそのスタッフの手を消毒してあげてから、来訪者自身は消毒せずに平気で会場に入る。爆笑。(不謹慎ですみません。みなさんはちゃんと自分の手を消毒してください。)
このときの「手」の所有者は、上記の場合と同様、動作主と一致する。命令文の場合は聞き手である。「あなたの手」を意味しているが言語化していないのを、わざと「わたしの手」と解釈して行動したところに笑いを生むしかけだ。所有表現のうちでも身体部分である場合は、誰かの身体の部分なので、とくに所有者との結びつきが強く、所有を言語化するとかえっておかしい。それは、「彼は手を持っている」と言えないこととも同じ原理だ。
所有表現として見れば、親族名称も身体部分と同じで、上記の例で「夫」は英語ではmy husband「私の夫」となろうけれども、「夫」というと、必ず誰かの夫である。ここでは自分の夫であることをことさらに言語化する必要がない。
冒頭の例を複文にしてみよう。「彼は帰宅したら手を洗った」は、英語では「帰宅する」従属節と「手を洗う」主節にそれぞれ主語をおかなければいけない(He washed his hands when he came home)。では、次のように助詞を変えるとどうだろうか。
(ア)彼は帰宅したら手を洗った。
(イ)彼が帰宅したら手を洗った。
(ア)が彼一人の話であるのに対し、(イ)の場合、手を洗ったのは彼以外の誰かだ。先行文脈に指示対象があればそれを指し、文脈がなければ話者と解釈してよいだろう。主題をあらわす助詞ハの及ぶ範囲が文末まで至るのに対して、ガは「帰宅したら」までしか及ばない。こんなところにも、主語を言わなくてもわかるしくみがある。
実際の文章の中ではどうなのか、いくつかの言語を比べてみた。原文がドイツ語の小説、フランツ・カフカ『審判』の冒頭部分の日本語訳(太田2007)では、原文の人称代名詞が「省略」されて、いわゆるゼロ代名詞として訳されている。それを( )に入れて補うとしたら、次のようになる。構文の違いなどにより1対1に対応しない箇所もあり、ドイツ語の関係節や並立して続く文で主語の代名詞がない場合は「/ ø」で示している。
(1)誰かがヨーゼフ・Kを誹謗したに違いない。(2)(彼が)何も悪いことをしていないのに、(3)(彼は)ある朝逮捕されたのである。(4)(彼の)部屋主グル‐バッハ夫人の賄い婦が、毎朝8時には(彼に)朝食を持ってきてくれるのに、(5)(彼女は/ ø)この日はやってこなかった。(6)こんなことは一度もなかった。(7)Kはもうしばらく待ってみた。(8)(彼の)ベッドに寝たまま(9)(彼は/ ø)外を見ると、(10)(彼の)向かいに住む老婆が(11)(彼女には)珍しく好奇心をあらわにして(12)こちらを(/彼を)観察している。(13)そのうち、(彼は/ ∅)どうも様子が変だと思い、(14)(彼は/ ∅ )同時にまた空腹も感じたので、(15)Kは(/彼は)ベルを鳴らした。
この不均衡が、イタリア語訳やスペイン語訳では半分ぐらいに少なくなる。というのは、日本語と同様、主語の代名詞がゼロ代名詞になるからだ。
これらのロマンス語では、動詞の活用が人称三つとそれぞれの単数・複数で、合計6つの活用パラダイムがあり、それに加えて時制や法によってもまたパラダイムを作る。つまり、人称代名詞を言わずとも、動詞の形態によってわかるのである。実際にゼロ代名詞であることも多いし、代名詞が後置されたり、強調形にされたりもする。
日本語と異なるのは、そのように主語をゼロ化する言語であっても、所有格や目的語の場合には、代名詞で受ける。その意味で、ロマンス語訳で使用される代名詞の数は、全ての格を代名詞に言語化するドイツ語と、格を区別せず「省略」する日本語との間に位置する(仁科2019: 478)。
前回のエンパシー階層を思い起こされたい。最も上位の言語行動の当事者は、上記の例にもあったように、省略されやすい。また、この階層は話題になりやすさの階層でもある。主題となった主格の代名詞が日本語ではゼロ代名詞となることは、話題になりやすさが省略されやすさとも相関するということを表す。
では、日本語は、ロマンス語のような動詞と人称の一致があるわけでもないのに、なぜ意味が通じているのだろうか。ゼロ代名詞の指示対象が、それ以外の要素に表されていることを以下に見る。
上記のカフカのテクストの日本語訳では、ダイクシス表現、すなわち、移動動詞の複合語「持ってきて」(4)や「やってこなかった」(5)、場所を直接示す「こちら」(12)のように、主人公Kの立ち位置を中心に、中心に向かう「来る」や、コソアドの「コ」によって、出来事が描写されている。加えて、「持ってきてくれる」(5)の「くれる」という補助動詞は主人公Kのために誰かが持ってくることを示す。そのようにして、主人公の視点から出来事が語られていることがわかる。
また、「賄い婦」や「老婆」が出現して、主語が変わるときには、助詞「が」でマークされており、「K」が再現するときには「は」とともに現れる。主人公Kは冒頭ですでに導入されていて、その後はこの文章の主題としてずっと「省略」されることで基底となる流れを作っている。
さらに付け加えるならば、賄い婦や老婆の描写では「ている」が用いられ、動きのない状態の描写として物語の背景に置かれており、物語を前景で進めていくのは、主題となる主人公である。
このような文章構造が、代名詞を言わずとも、導入された主題としての主人公と、他の参与者を区別しているのである。(Nishina 2015)
このように、省略に代わる他の方略もあって、そこでしっかり言語化しているのである。
日本語は省略が多くてあいまいだというのは、人称指示を明示する言語を母語とする学習者にとってそう思われるのであって、指示関係を言語化する方法は他にもある。
日本語の場合は待遇表現もあり、同じ「行く」という行為でも、「いらっしゃる」「伺う」など敬語によってその動作主体がわかるしくみもある。所有関係についても、「主人」と「ご主人」といった形態的な方法、「御社」と「弊社」などの複合語、「奥様」と「家内」などと語彙的に区別する方法もある。
方略のあり方は言語によって異なる。
日本語では動物も人間も、声を発するとすべて「なく」としか言えない。漢字で書くときにかろうじて「泣く」と「鳴く」を区別する程度だ。印欧語をはじめ、アラビア語などの他の言語では、その動物によって動詞がある。たとえばドイツ語で、猫はmiauen、犬はbellen、馬wiehern、豚はgrunzenなどなど、オノマトペを思わせる語幹のものもあり、30ぐらいの動詞はすぐに挙げられそうだ。動詞だけ見れば動作主体がどの動物かわかるのだ。(余談だが、動物の鳴き声が人にも転用される。狼を表す動詞が、ドイツ語でもイタリア語でも人間が泣き叫ぶ様子を表すのもおもしろい。)日本語でも動詞として「吠える」「いななく」「囀る」ぐらいの言葉はあるが、動物の鳴き声を区別するには擬声語を副詞的に用いて、ワンワンなく、ヒヒーンとなく、というふうに動作主体を表現する。日本語の擬声語の豊かさは裏返してみると動詞の乏しさを反映しているということだ。ドイツ語はその逆で、擬声語はあるが、辞書に載るほど語彙化されているわけではないし、話者が共有できるようなものも動詞に比べればずっと少ない。
こうやって世界の言語はそれぞれに表現手段のバランスをとっているのだなあと、時に感慨深くなる。言語の方略にはいろいろあって、省略など、言語化されないこともその一つであることがわかる。
最後に、思い出話をひとつ。具体的に言語化されていないことで指示対象がきまる話。
ハイデルベルク大学言語学科の一般言語学の教授、Klaus Hegerは、夕方2つの授業を続けて開講していたが、議論が白熱してくると、「これについては3つめの授業で議論を続けましょう」と言っていた。筆者が初めてこれを聞いた時、授業は二つしかないのに、このdie 3. Sitzungとはなんだ?と不思議だったが、それは、2つの授業の後、皆で近くのお店に繰り出して、飲んだり食べたりしながら議論を続けることが暗黙の了解だったのだ。
その店は、誰も予約をしたことはないのに、一番奥のテーブルが常に我々のために予約席となっていた。そして注文を取りに来たオーナーに、Heger教授はきまって言うのだった。「Das Übliche」。
Das Üblicheとは、üblich「ふつうの」「よくある」という形容詞を名詞化したものである。料理を注文するのに、「いつものをください」と言ったわけだ。
そして、出てくる料理は毎回違うものだった。
「いつもの」の指示する対象がその都度、異なる。「いつもの」と言うのだから、ある決まったものを指すと思ったら、実際には、不定indefinitの指示対象referentだったわけだ。でも、いつも不定なのであれば、それもやはりいつものものなのか、筆者の頭の中で、発話の意味、意図、指示、定性、などのような言語学的概念がぐるぐる回っていたことを覚えている。
Heger教授は、毎回、とても楽しそうにそれをやって、店の主人も学生たちも、みんな同様に楽しんでいるようだった。それは教授が急逝される直前まで、何十年も続いたルーティーンだった。
残念ながら筆者自身にはいまだにそのような食べもの屋さんがない。いつ行っても「いつものをください」と言えば、多様な料理で豊かな食生活ができるようなお店が。
-
- 2021年06月01日 『言語のダイバーシティ 9. エンパシー階層 仁科陽江(広島大学)』
-
9. エンパシー階層
ミラーニューロンについて耳にされたことがあるだろうか。
人が他者の行動を見た時、自ら行動するときと同様に活動電位を発生させる神経細胞のことである。単に行動の感覚特性に「鏡」のように反応するばかりでなく、その意図まで処理しているとも言われ、他人のことを我がことのように瞬時に理解・共感することを可能にする。
今回は、その共感が、言語に反映されて、文法など、言語構造も決めていることを紹介する。
前回、意志を持たない無生物の非使役者が与格を取りにくいという例で「*魚に腐らせた」という例をあげた。(つい、無生物と言ってしまったが、理由がないわけではない。)生物学的には魚や鳥や四つ足の動物は有生物だろう。が、人と魚では、言葉にするときの扱い方が異なる。それには、共感のあり方が異なることにも一因がある。同じ魚でも、水槽に飼っている魚と腐った魚、同じ動物でも、家族のようなペットと野生動物とでは、共感のあり方が異なるだろう。命のない無生物であれば、さらに共感度が低くなる。
最も共感できるのは言うまでもなく自分自身であり、言語活動においては、相手も当事者である。話題になっている第三者がそれに続き、人、動物、無生物というふうに、次のような階層ができる。
話し手・聞き手>第三者>有生物>無生物
これは、有生性の階層animacy hierarchy(Comrie 1989)としても知られており、このような階層を構造化する要素である共感によって、有生物や無生物を連続的に階層化できる。日常の言語である「共感」と区別する意味で、ここではエンパシー階層(Lehmann 2002)と呼ぶ。(右上図を参照。クリックで拡大)
このような区別が言語構造のなかに多かれ少なかれいろいろな形で組み込まれていることが、多くの言語においてわかっている。
メキシコのユカタン半島で話されるマヤ語族のユカテコ語では、他動詞に主語・目的語が人称接辞によって表示される。多くの言語では、その接辞の順序が、主語や目的語という統語機能によって決まるが、ユカテコ語では、その順序は、(1)と(2)の例のようになる。動詞接辞の-e’xは2人称複数、-o’bは3人称複数を表し、主語、目的語のうち、階層の上位にあるものを指す動詞接辞が先行する。(1)は2人称複数が主語、(2)は3人称複数が主語である。
色々な組み合わせを検証した結果、この言語では動詞接辞の並び方が、統語機能によるのではなく、エンパシーの高い順であることがわかった。 (Lehmann 2002)。
(1) t-a hats' -e'x -o'b
[過去]-[主・2] 殴る -2.複 -3.複
「君たちが彼らを殴った。」
(2) t-u hats' e'x -o'b
[過去]-[主・3] 殴る 2.複 3.複
「彼らが君たちを殴った。」
同じ人間を表す名詞でも、ナバホ語では成人と子供を区別する。Diné’ ashkii y-oo’į́「男が少年を見る」の文は、主語であるdiné’「男」の階層が高く、動詞接辞-yが用いられる。Ashkii「少年」が上位に来てdiné’「男」に先行する場合は、Askii diné’ b-oo’į́となって、受身表示のようなb-が用いられる。そのような動詞形態によって、この言語の名詞は、人間>子供/大動物>中動物>小動物>自然力>抽象概念に至る分類がされる。(Young & Morgan 1987: 65-66)
無生物のなかでも、具象的な対象の方が抽象概念よりも階層が高く、集団よりも個人、普通名詞よりも固有名詞、不特定の対象よりも特定の対象の方に共感しやすい、ということも言語に現れる。その現れ方は言語によって様々である。
この階層が数のカテゴリーの言語表現に現れる例を挙げる。英語やドイツ語のような印欧語には、日本語や中国語にはない数の概念があって、単数・複数の対立があると言われる。
が、実際には、中国語の「们」、日本語の「たち」のように複数を表す接辞がある。ただし、その使用範囲は、「私たち」「先生たち」のように人を表す名詞に限られる。「猫たち」「鳥たち」と動物にも使えるだろうが、「?木たち」など植物では言いにくく、「*机たち」のような無生物に使うことはできない。
では、機械であるロボットはどうか。本が好きな人なら、「私の大切な本たち」と、言うことに抵抗は少ないのではないか。
そこが生物学的区別とは異なり、境界は連続的であり得る。車は無生物だが、「あそこに怪しい車がいる」と、有生物の存在を表す「いる」という動詞を用いて表現できる。物を擬人化して語ることもある。
数のカテゴリーを持たないと言われる日本語の名詞が複数を表現できるのと逆に、印欧語においては、複数にはならない名詞もある。英語のbeauty「美」やドイツ語のHaß「嫌悪」などの抽象名詞は複数にできない。Beautiesと言えるとしたら、それは美しい人や景色といった、普通名詞の意味で使われているので、階層はもっと上がる。
特筆すべきは、この階層が含意の普遍性を持つ階層として捉えられることだ。ある言語において、階層上のあるステージで複数が作れれば、その言語ではそれより上のすべてのステージで複数を作ることができる。
この含意の普遍性のエビデンスを通言語的に見出すことができる。たとえばグアラニー語では1・2人称だけに単複の区別が見られ、ウサン語は3人称を含めた代名詞だけに、ティウィ語では人間を表す名詞以上、カーリア語では有生物以上のステージで単複の区別が見られる。
上記の階層の図では、これらの言語が単複を表すステージの重なりを色の濃さで示している。
言語において有生か無生かで区別されることが多岐にわたることは、これまでの連載でも、文法上の性を含む名詞の類別、構文と格などの例を挙げてきた。
ロシア語の名詞屈折のパラダイムの中では、男性名詞の対格が、有生物では属格genitive(ロシア語学では生格と呼ぶ)を取るのに対し、無生物では主格と同じ形式である。他動詞文において主格で表される主語の意味役割は、典型的には動作主であり、動作主は典型的には意志を持った有生物である。無生物は動作の対象になりやすく、動作主として主格になりにくいのであれば、形式上ことさらに区別する必要がない。
この動作主になり易さ、あるいは動作の対象になり易さの度合いが名詞句階層(Silverstein 1976)として表されたのは、エンパシー階層の考え方に至る草分け的な研究であった。このような階層は、ある言語の格組織全体を体系づけて説明することを可能にする(角田1991)。
また、話題になり易さや関心の度合いといった考え方も、エンパシー階層と共通する要素を持つ。
ロマンス語が直接目的語を有生性によって区別する場合は、スペイン語ではveo a esa persona「あの人を見る」の目的語esa persona「あの人」に前置詞aがつき、ルーマニア語でも同様に前置詞peがつく。このような対格標識に対して、無生名詞は無標である。
ゲルマン語族のドイツ語では、前置詞の目的語が代名詞化するときに、有生性の区別がある。Ich bin mit dem Lehrer / mit dem Unterricht zufrieden 「私は先生に/授業に満足している」と言うとき、前置詞mitの目的語であるLehrer「先生」もUnterricht「授業」も男性名詞であるが、男性・単数・与格の代名詞ihmを取るのは、有生名詞の場合だけである。無生名詞は複合的に副詞化(da-mit)する。Ich bin mit ihm / damit zufrieden.
有生性のこのような区別は定性とも密接な関係を持つ。ヒンディー語は、目的語を後置詞-koで標示するが、対象が人間で定の場合は義務的に、非人間で定の時も典型的に用いるが、非人間で不定の場合に用いることはない(Comrie 1989)。
定性の区別については、トルコ語の対格語尾は目的語が特定のものに限定されるときに用いられる。不特定の時には語尾がつかず、裸の基本形、つまり主格の形と同じである。
同じアルタイ語族に属するモンゴル語の-iig、トルコ語との影響関係が見られる現代ペルシャ語の-raも定性上の区別をする対格語尾である。中国語は孤立語の構造を持つが、目的語に前置詞「把」をつけて語順を変えることで、同様の機能を持つ。
定性について言えば、エンパシー階層の最上位をなす言語活動当事者は常に定である。3人称の代名詞も指示対象を持つ定である。
定性definitnessと指示性referentialityの階層を、エンパシー階層に関連して、次のようにまとめることができる。
定definit > 特定indefinit, specific > 不特定indefinit, non-specific
代名詞pronoun < 固有名詞proper noun < 普通名詞common noun
対格標識の例で見たように、無生であり、不定であることは、相関する。
とらえどころのない不定の対象よりも、限定できる対象の方が、普通名詞に対する固有名詞のように、エンパシーもまた高い。話題になり易さというのは、定性の高い場合であり、関心の高さは、自分や自分の周りの人が最も高いと言える。
エンパシーの高いものは、談話の中で主題化されやすく、話者の視点を形成しやすい。逆に言えば、ナバホ語の例でも見たように、逆行態や受動態などの統語的な操作によって、本来階層の低いものを主題化させることが可能になり、それゆえ、テクストの情報構造を担う役割も持つ。
このように、エンパシーについては、有生性、定性、指示性とともに階層をなし、統語的な振る舞いや談話の構造に反映していることがわかる。
連載第7回に、「ウエーターがゲストに一杯の水を取ってくれる」というクレル構文を扱ったが、ここでは同じ3人称の参与者のうち、ゲストの方にエンパシーがあると言える。
結合価を上げるという機能は、アゲル構文にもある。「ウェーターがゲストに一杯の水を取ってあげる」と言うときはウエーターの方にエンパシーがあることで対立をなす。
従来、日本語の授受表現が話者の視点で説明されてきたのは、エンパシーが視点を形成するということと矛盾しない。クレル構文では受益者beneficiaryが、アゲル構文では授益者benefactorが、エンパシー階層の話し手のステージにまで引き上げられようとすることで、話し手の立ち位置がきまるのである。
日本社会にはウチ・ソトの区別があると言われている。それが日本語に反映されているのが、たとえば二種類の敬語の使用である。会社の社員が、社長に向かっては尊敬語を使うが、社外の人に対しては、社長を呼び捨てにし、謙譲語を使う。前者では社長はソト、後者ではウチの存在である。ウチの方が話者である1人称に同等もしくは近くなる、つまりエンパシー階層の高い位置を占めるということになる。自分の領域にあるかどうかで言動が区別されている例である。
その区別は、「情報のなわ張り理論」(神尾1990)として展開された考え方にも通じるであろう。この理論は、与えられた情報が話し手のなわ張りに属するかそうでないかで、言語表現が規定されていることを、様々な言語現象において示したものである。具体的には文末表現や省略などを例示し、情報の扱いについて心理的距離という観点から論じている。
ウチ・ソトの区別やなわ張り理論は日本語の特徴として語られてきたが、話し手の領域を他者と区別し、その関係が言語によって操作されていることは、エンパシーの現れとして理解しやすい。
エンパシーやその階層は、人間の自然言語である限り、どんな言語にも見られる普遍性のあるものだといえる。それゆえに、さまざまな言語現象を説明することを可能にする。
人間の認知機構の働きが、言語に現れ、言語を通してそのからくりが垣間見られるところに、人間の基本的な営みとしての言語活動を再認識させられる思いである。
今回取り上げたエンパシーの考え方は、人類の、あるいは霊長類などさらに広い認知主体において、言語による言動のみならず、行動様式一般とも関連することは容易に想像できる。他者との関係、情動や認知のメカニズム、その神経基盤など、学術的にも他分野との融合、学際的研究が期待される。
グローバル化の進む昨今、他者への共感、思いやりが、人々の言動を変容し、より良い共生社会を形作っていくことを願ってやまない。そのためにも、言語研究の意義を感じる今日この頃である。
-
- 2021年05月25日 『言語のダイバーシティ 8. 構文と格 仁科陽江(広島大学)』
-
8. 構文と格
前回、結合価について述べたが、これを利用して、人をからかうクイズを一つ。
「法隆寺を建てたのは誰でしょう。」
「聖徳太子」と即答したあなたは、学校で歴史の時間にちゃんと学習した方とお見受けする。残念でした、というわけで、ここでの答えは「大工さん」。聖徳太子は大工さんに建てさせたのであって、自らノミとカンナを持って建てたわけではない。それでも聖徳太子の意志が法隆寺の建立を実現させたのであるから、聖徳太子が法隆寺を建てた、とも言えるのは確かである。
結合価が二つしかなければ、建てたのは大工さんか聖徳太子か、どちらかに決めなくてはならない。そこにクイズが成り立つからくりがある。どちらかが正しいとも間違っているとも言えないから、回答者が聖徳太子といえば大工が正解、その逆も然り、と人をからかうには十分である。
(言語学をやっていれば、クイズとかお笑いとかのネタが大量生産できるというのが筆者の持論だ。これについてはまたどこかで改めて紹介してみたい。)
「聖徳太子」と「大工」の両方を法隆寺が建立されるという事象に参与させようとするならば、使役文にすれば結合価が増えて、二人とも文の必須項として取り込める。
それができるのは使役文の持つ複合的な構造による。使役者による原因となる事象が先行し、被使役者による行為という結果が従属する。
前回、連載第7回の例で、必須項の出現順序が、ガ > ヲ > ニ となっていたのを想起されたい。これらに使役者「先生」を加えてみると、被使役者の格が一つずつずれて、最後に斜格を加えることができる。
太郎が来た 先生が太郎を来させた。
太郎が本を買った 先生が太郎に本を買わせた。
太郎が花子に本を送った 先生が太郎から花子に本を送らせた。
つまり、すでに使われている格助詞を「*太郎を本を買わせる」のように重ねて使うことができないのである。もう一人増やしてみよう。先生が次郎に働きかけて、次郎が太郎から花子に本を送らせたとしたら、格助詞ではなくともそれに準ずる形式を用いて「先生が次郎をして太郎から花子に本を送らせた」のような文もできるだろう。つまり、以下のように被使役者の格階層ができる。
ヲ(直接目的語) > ニ(間接目的語) > カラ(斜格) > ヲシテ(複合辞)
日本語は-(s)aseru(セル・サセル)で使役構文を作るが、その意味合いは、強制的にさせるものから、説得や指示によるもの、許してやったり、放っておいたりするなど、使役者の関与のあり方によって異なる。また、使役者が意図しないで、「魚を腐らせた」とか「子を早く死なせた」など、その事態を止められなかったという消極的な関与であっても使役構文を使うことができる。
スロベニア語やセルビア語などの南スラブ語は、日本語のような使役を表す形態的な手段を持たず、その意味合いに沿って、たとえばセルビア語では、naterati(強制する)、narediti(指示する)、dozvoliti(許可する)などの動詞を用いることで、語彙的に表現しなければならない。
使役構文が文法化していても、いくつか機能分化があって、日本手話では、使役構文を作る役目を「わかる」「OK」「かまわない」などの語彙が担い(岡・赤堀2011: 75f)、中国語では「叫」や「让」や「请」などを用いて、それぞれ強制や許容や依頼の意味を区別している。
英語のmakeとlet、フランス語のfaireとlaisserをはじめロマンス語における同様の対立は、強制や説得という使役者の積極的な働きかけに対して、許容や放任の意味で大きく区別している。
二分した使役表現を持つ言語が多いのは、参与者の意志のありかを区別しているからともいえよう。
日本語にはそのような区別が述語にこそないが、格助詞を変えることで、違いが現れることがある。上の例での自動詞の使役において、「太郎を来させる」に対して「太郎に来させる」とも言えて、その場合は、太郎が来たいのでそうさせてやったという許容のニュアンスが強くならないだろうか。最近の若者たちはこういう区別をあまり感じないらしいが。
上記のセルビア語においても、原理としては同じことが言える。以下の例は両方とも「母は子供に水を飲ませた」と、日本語の使役文に訳せる。使役者majka「母」の意志や働きかけの強いnaterati「強制する」という意味であれば、被使役者「子供」は対格deteをとり、命題da pije vod-u「水を飲む」に対する意志が被使役者にあって、母がそれに従う場合は与格det-uをとっている。日本語のヲとニの対立と比較して、この現象は偶然ではないと思われる(例文はシュタインバフ2017より)。
(強制) Majka je natera-la dete da pije vod-u
(許容) Majka je dozvoli-la detet-u da pije vod-u
意志のありかが異なるという考え方は、意志を持たない無生物の被使役者が与格を取りにくいことにも表れている(「*魚に腐らせた」)。
また、「太郎を車から降りさせる」と使役文にせずに、「太郎を車から降ろす」と他動詞にすると、対格の目的語しかとれず、太郎の意志を尊重しないで有無を言わさず直接手を下す姿が想像される。同一言語の中でも、このような類像的なヴァリエーションが見出される。
このような格の表す関与のあり方の違いは、使役文より使役性の弱くなった、願望を表す構文にもよく現れる。日本語では、自分の願望を「〜たい」で表すが、他者に対する願望であれば、「〜てほしい」を用いて構文化されており、文の構造としては使役文と同様である。実際に原因となる行為を行わずに、結果が起きることを願う場合も、命題を遂行する参与者が存在して、同じ構造を取る。ただし、願望の文では、この参与者が主格と与格で現れる。
以下の例文は、筆者が日本語母語話者を対象に、小さな調査を行ってみたときの例文からの抜粋である。格助詞ニとガのペアのうち、どちらを使うか、という質問に回答してもらった。
雨に降ってほしい。
雨が降ってほしい。
猫に安い餌を食べてほしい。
猫が安い餌を食べてほしい。
ずいぶん前の調査だったので、詳細についてのデータをここに示すことはできないが、回答としては、雨の例ではガ(「雨が降ってほしい」)、猫の例ではニ(「猫に安い餌を食べてほしい」)が多かった。が、「猫が安い餌を食べてほしい」という回答もあり、最も少ないのは「雨に降ってほしい」であった。
ある子供は、「〜てほしい」の文は全部おかしい。「猫に安い餌を食べさせたい」としか言えない、と回答した。
雨の例については、有生性と意志性で説明できるだろう。「雨に降ってほしい」というと、雨に向かって、明日降ってください、と頼んでいるようなニュアンスがある。雨に対して影響力は持てないので、雨を主格で表すのが自然だということだ。そこでは、話者が事態をコントロールできるかどうかが問われる。英語でも、I asked that he leaveとheを主格でいうときは、I asked him to leaveというときほどのコントロールがない。さらに、使役の助動詞を用いてI made him leaveとすると最も影響力は強い。
「猫が安い餌を食べてほしい」と答えた人は、願望する話者のコントロールを放棄しているようで、きっと猫の自由意志を尊重する愛猫家なんじゃないだろうか。「猫に安い餌を食べさせたい」と言った子は、動物に対して自分が最も影響力を行使するという、支配的な性格なのかなあ、と感じたのであった。
そういうことを考えると、助詞や構文の選択によって、ちょっとした性格判断ができるのではないかと思ったりする。
合コンやお見合いの場で、初対面の人の性格の判断には、楽器を弾かせるか車を運転させるかするとよくわかると、筆者は常々思っているのだけれど、誰もが楽器を弾くわけでもないし、運転するわけでもない。が、日本語を話す人であれば誰でも、その言葉の使い方から考え方や性格も見えてきて、人相や手相よりももしかしたら当たるかもしれない。
(これも言語学をやっていれば便利なことの一つだ。)
-
- 2021年05月18日 『言語のダイバーシティ 7. 結合価 仁科陽江(広島大学)』
-
7. 結合価
言語学の用語には、他分野から流用されたものもある。
結合価valencyというのは、元々化学の原子価のことで、元素が他の元素と結びつく際の結合手の数をいう。H2O(水)においては、酸素原子Oの原子価は2価、つまり結合手が2本あるので水素原子Hを2つ結合することができる。同様に、NH3(アンモニア)では窒素原子Nの結合価が3価なので水素原子Hが3つ、HCl(塩化水素)では塩素原子 Clが1価なので水素原子Hは1つ、ということになる。
そういえば学校で化学の時間に、こんなことを習ったという記憶もおありだろう。
この結合価が、述語を作る動詞や形容詞と結びつくことのできる項の数を表すものとして、フランスの言語学者リュシアン・テニエールによって言語学に導入された。日本語で具体的に考えてみると以下のようになる。上で述べた化学の例も添えておく。
(1)花子が走る HCl
(2)花子が太郎を殴る H2O
(3)花子が太郎に手紙を送る NH3
「花子」「太郎」「手紙」が水素原子Hにあたる項argument、動詞「走る」が塩素原子Clにあたる一項動詞、「殴る」が酸素原子Oにあたる二項動詞、「送る」が窒素原子Nにあたる三項動詞であるという考え方である。
ちなみに、項が増えるに従って、格助詞の出現順序が「が」>「を」>「に」となっているところに統語階層の原理が反映している(前々回参照)。
動詞が要求する必須項というのは、それが欠けると不適格な文となるものと考えればよい。「置く」の場合は、置く人、置かれるもの、それに、どこに置くかという場所も必須だ。場所を特定せずに*He placed the cupとは言えない。「行く」goには目的地が必要で、それがない場合はgo awayとか「どこかへ行った」と不定の場所を示す。
必須項は文脈によって省略されることもあるが、たとえば、*(She) hits *(him)やgo *(there)というように英語の代名詞の義務的な使用にも結合価が言語化されていることがわかる。(省略するのが非文法的だという意味で( )の前に*をつけて示す。)
言語によっては、二項動詞や三項動詞を作る手続きがある。
トルコ語には「殺す」という動詞がないので、「死ぬ」ölmekという動詞に使役の接辞-dürをつけてöldürmek「(〜を)死なせる」としたり、アイヌ語では「与える」という三項動詞がないので「持つ」korに使役の接辞-eをつけてkor-e「(〜に〜を)持たせる」と表現したりする。
中国語のような孤立語では、動詞の結合価が一部を除きほぼ全て1価か2価なので、動詞句を並べて、動詞連続構文を作る。西アフリカの言語にもそのような構造がよく見られる。ヨルバ語では「彼が私に金を与える」という三項動詞の文を、二つの動詞句で一つの文にして表す。以下の例でf-は動詞fiの縮約した形である。
(4) Ó f-owó fún mi
彼 取る-金 〜に与える 私
「彼は私に金をくれた」
このように結合価を変える文法的な方略がある。結合価を増やしたり減らしたりする方法は、世界の言語で非常に多様だ。
結合価を減らす手続きで、我々がよく知っているのは、英語の時間に習った受動文だろう。能動文の目的語を主語にして、主語であった動作主は前置詞句に後退し、省くこともできる。The purse was stolen「財布が盗まれた」という時には財布に焦点があり、誰が盗んだかを言語化する必要はない。
以下にあるのは、ブラジルの先住民族によって話され、すでに絶滅したとされるトゥピ語の例である。(5)の目的語s-oβáが(6)ではそのまま動詞に取り込まれ、主語がマークされた動詞句になっている。(Bauer 1988: 44)。この例では目的語を動詞に抱合することによって結合価が減っている。
(5) s-oβá a-jos-éj
[3単・所有]-顔 [1単]-[3単]-洗う
「私は彼の顔を洗った」
(6) a-s-oβá-éj
[1単]-[3単・所有]-顔-洗う
これは、抱合語incorporating language(ないしは複統合語polysynthetic language)に特徴的な統語上の手続きで、そのように抱合された名詞は不定であることも多い。
日本語で「顔を洗う」を「洗面する」と言うと、目的語がなくなり結合価は減るが、動詞句を名詞化してサ変動詞にしたものであり、英語でbabysit「子供のお守りをする」やドイツ語でstaubsaugen「掃除機をかける(ほこりを吸う)」というのは、名詞babysitterやStaubsaugerから動詞に逆形成したものと考えられるので、厳密には名詞抱合とは違う種類のものである。
逆に、結合価を増やすために、道具、場所、参与する人など、必須でない意味役割を目的語に繰り上げ、結合価を増やす構文applicative constructionがある。
スワヒリ語では、tok-a「来る」や、end-a「行く」という動詞に、結合価を増やす接辞-eをつけ、それぞれ、tok-e-a「〜から来る」end-e-a「〜へ行く」のように、場所名詞を直接目的語にする。
インドネシア語では、動詞に接辞-iをつけて場所や受取人を、接辞-kanをつけて道具や受益者を、それぞれ直接目的語に昇格させることができる。
では、どうしてこのようにして結合価を増やすのだろうか。増やすことによって、何が変わるのか。そこには文法と意味に直結する機能がある。
次のインドネシア語の例では、動詞に-kanをつけることによって、tamu「ゲスト」が目的語として加わった。
(7)Pelayan mengambil-kan tamu seglas air
ウエーター [他動].取る-[受益] ゲスト 一杯 水
「ウエーターはゲストに一杯の水を持ってきた」 (Sneddon 1996:80)
-kanのないベースとなる文は、「ウエーターが一杯の水を取る」というもので、ゲストは不在である。が、接辞をつけることで全体の構造が変わる。
これは、日本語にもあることで、補助動詞「くれる」をつけると、「ウエーターが一杯の水を取ってくれる」となり、参与者が増えることがわかるだろう。ウエーターと水と、そしてもう一人、その人のためにウエーターが水を取った、第三の項となる人物の存在が明示される。それは述語の要求する三つ目の項として助詞ニをとる。「くれる」がなければ、「??ウエーターがゲストに一杯の水を取る」とは言いにくい。そこでは「ゲストのために」という具合に、付加詞的に修飾する要素adjunctにしかできない。ここに文法的な違いがある。
ヨルバ語では(4)のほか、以下の三項動詞文も可能である。ここでのl-は、(4)でのf-のように、場所を表す動詞から短縮し文法化した前置詞のような働きをして、間接目的語をマークする形になっている。日本語では「魚を」という直接目的語に相当する。
(8) Mo fún un l-ẹ́ja.
私 与える 彼 [目的語]-魚
「私は彼に魚を与えた」
ヨルバ語のこの文がmo fún unをベースとするとすれば、日本語の統語階層構造とは異なる。
この両者の違いはドイツ語ではバリエーションとして、以下のように動詞schenkenとbeschenkenの対立がある。
Er schenkte mir den Fisch. 「彼は私に魚を贈った」
Er beschenkte mich mit dem Fisch. 「彼は私に魚で贈り物をした」
動詞の前綴りbe-による手続きは、1人称単数与格の人称代名詞mirを対格michに昇格させ、対格の直接目的語den Fisch「魚」を前置詞句mit dem Fischに降格させる。相手に贈り物をすることが強調され、何を贈るかは二の次であるニュアンスがある。
同様に、kochenは「料理する」という動詞であるが、それに前綴りのbe-をつけることで、目的語になるものが、料理ではなくて、その料理を食べる人となる (Ich bekoche dich mit dem Fisch)。つまり、何を料理するかというよりも、誰のために料理するかが問題なのだ。息子が疲れて帰ってきたから、何か美味しいものを作って食べさせよう、という場合がこれである。
このように、動詞の項に割り当てられる文法関係を変えることで、意味の違いも生んでいる。
動詞の結合価とその操作について、おわかりいただけただろうか。
トルコ語では、相手が理解したかどうかを問うのに、「わかる」を意味するanlamakに使役の接辞-tのついた形を用いるそうだ。つまり、私があなたをわからせたか、という形式にする。Do you understand?と聞かれて、理解できていない時には罪悪感を感じたものだが、トルコ語のようにanlatmakで尋ねられると、理解できないのは私のせいじゃない、と思わせてくれる。わかることのできない私以外に、もう一人わからせてくれる人がいる。結合価が増えて、なんとなく嬉しい。
-
- 2021年05月11日 『言語のダイバーシティ 6. 色彩語彙 仁科陽江(広島大学)』
-
6. 色彩語彙
太平洋に浮かぶ島でフィールドワークをしていたGunter Senftという言語学者から何十年も前に聞いた話。語彙リストを作るべく、現地で色彩語彙について聞き取りを行なったときのことである。
真っ青な空を見て、あれは何色か、と尋ねて、答えたことばを「青」とメモし、次に海岸へ行って真っ白な砂浜を見て、これは何色か、と尋ねて、「白」とメモしていると、さっきの「青」と同じ言葉なのだという。からかわれているのかと思ったら、彼らにとっては同じ色として表現することがわかった。
世界には色彩語彙が二つしかない言語もあって、ニューギニアのダニ語はmolaとmiliの2語によって全ての色をカバーしているという。我々の言葉で言えば、暖色系と寒色系の二つに大きく分けたような、あるいは「明るい」と「暗い」を対立させたような範疇化だ。
なんてプリミティブなんだ、などと言っているそこのあなた、日本語も実はそう変わらない。日本語学習者が驚くことはいろいろあるけれども、形容詞の少なさもその一つ。
日本語には色彩形容詞が4つしかない。「白い」「黒い」「青い」「赤い」の他は、「黄色」「茶色」「灰色」など、色をつけた複合名詞である。色を表す語彙というより、お茶や灰という、その色を持つ事物を色彩の名に使っているにすぎない。もっと細かく分けるならば、「こげ茶色」「深緑」と修飾したり、カーキ色など、外来語を使ったりすることもある。
日本工業規格(JIS)で規定されている色彩名称は298あるという。ドイツの文房具の老舗Faber-Castell社の120本入り色鉛筆にはそれぞれに色名がついていて、caput mortuum「死んだ頭」などという紫色の名前もある。
筆者の明治生まれの祖母は、おそらく5つほどの色彩語彙で足りたのではなかったかと思う。4つの形容詞のほか、黄色はキーナ(黄な)という形容動詞だった。子供の頃、この前着ていたアケー(赤い)服が可愛かったと言われ、赤い服を着た覚えがなくて話が通じなかったことがあった。「赤い服」は茶色だったのだ。アケーはまた、早朝、「もうアケーか、アコーなったか」というときには「明るい」も意味していた。音便化したアウェーは「淡い」とも「青い」とも解釈できる。クレーは「黒い」とも「暗い」や「昏い」とも。おばあちゃんは方言の限られた形容詞表現で、そんな風に色相hueだけでなく色の彩度saturationや明度lightnessも表現していたのかなと思う。「白い」が「著し」から来たと言われる説も含めて、日本では古くからそのように使われていたのかもしれない。
世界の色彩語彙について、Berlin & Kay (1969)は、約100の言語を調査し、基本色彩用語basic color termsの考え方を導入した。どの言語でも11の基本用語が階層的に出現するとし、ある言語に二つの色の対立しかない場合は、白と黒、もう一つ色が加わると赤、その次は緑か黄色、というように、以下の図のような階層をなす。日本語は11の基本色彩用語を持つとされるが、4つの形容詞が上位に位置するのがわかる。
white > red > green > blue > brown > purple
black yellow pink
orange
grey
I II III IV V VI
この基本色彩用語が結合して、ある色のカテゴリーとなることもある。日本人が英語で「青信号」をblueと訳して通じないというのはよくある話で、日本語の「青い」がgreenも含んでいるので、「青葉」「青竹」「青々とした新緑」などという言い方ができる訳である。中国語の「青qīng」は黄色も含むという。
上記のダニ語の例でも言えることだが、固有の言語において色彩を区別する色彩語彙が少ないほど、一つの色彩語彙のカバーする意味領域が広い。
階層のステージにローマ数字をつけると、日本語の古来の形容詞は、上位IVの段階までを占めることになる。
Berlin& Kayはこの11語彙の並びを進化過程として、時間的・進化的順序付けtemporal-evolutionary orderingがあるとしている。これは、前回扱った含意の普遍性として説明できる。固有の言語において階層上のある段階に基本色彩用語が存在すれば、それよりも上位の用語の存在が含意されるというものである。
では、この含意的階層関係が、固有の言語の文法とどのように関わるか、例を挙げて検証してみよう。
日本語では、色彩形容詞は4つしかないことを述べた。それはこの階層の上位にあり、緑は青に含めるとして、黄色と茶色が近くにある。この二つの色は、日本語古来の形容詞が「い」で終わるように、「黄色い」「茶色い」とも言えて、「黄色くない」「黄色かった」とク活用もし、今日ではほぼ完全に形容詞化している。上記では日本語の色彩形容詞が階層上のIVの段階までとしたが、この拡張を含めると、Vの段階までカバーできることになる。VIに属するものでは「灰色い」、「桃色い」などとは言えない。
ドイツ語ではどうだろうか。日本語の色彩形容詞の少なさに驚くドイツ人日本語学習者の母語には、確かに多くの色彩形容詞がある。それらは他の形容詞同様、付加語的用法で屈折し、「赤い本」ならばein rot-es Buch(= a red book)というふうに、修飾する名詞の性・数・格を表す屈折辞-esを形容詞rotに付けなければならない。
しかしながら、このような屈折をしない色彩形容詞がある。Orange「オレンジ色」、rosa「ピンク」、lila「紫」、beige「ベージュ」などである。形容詞語尾をつけず、ein rosa Buch「ピンクの本」となり、文法から逸脱しているように見えるのだが、特定の語彙については文法書でそのように定められている。
とはいえ、やはり語尾がないことに違和感を感じる話者も多いようで、特に話し言葉では、ein rosa-es Buchとされることがある。これらの語彙はロマンス語からの借用で、母音で終わる語が多いため、ein rosa-n-es Buchと、母音衝突を避けてnを入れるという特異な屈折をすることもある。
このようにゆれがあるのも事実で、さらには、より標準的に-farbig「〜色の」という派生辞をつけて形容詞語尾をつけやすくするという方法もある(ein rosafarbig-es Buch)。ラテン語ochraと語源を同じくするocker「黄土色」など、音韻の特徴が異なる語にも適用され、かなり生産的には使えるようだ。
もうお気づきのように、ここで問題となっている形容詞は、すべて階層のVIより上位にはない。VIの段階では、grau「灰色」だけが、ein grau-es Buchと、通常の文法にかなった屈折をする。その点では、grauは他のVIの構成要素と比べて既に上位指向を示している。
Grauは英語のgreyと同様、ゲルマン語に属する語彙として、他の借用語と系統を異にする。二重母音auが語末にあるのはドイツ語固有の語彙にもたくさんある。その意味でgrauはゲルマン語の文法とそぐいが良いとも考えられる。
あるいはそれが灰色という色の特質にあるのか、VIにあるのは上位の階層の色彩に比べて周辺的な中間色であるが、個々の色の特質で説明ができるのかどうかはわからないので更なる検証が必要である。
音韻の特徴から見れば、「白い」「黒い」「赤い」「青い」はすべて3モーラの拍を持ち、音節としては3つある。「茶色い」「黄色い」は4モーラではあるが、tyaiを二重母音、kiiを長母音のように考えると3音節になる。「灰色い」は5モーラになるが、これもhaiiと母音が重なっているところが、「桃色い」などとは異なる。「黄色い」や「茶色い」に追随する色があるとすれば、言いやすさの点では「灰色い」だろうか。「灰色」は「鼠色」とも呼ばれるが(そしてJISの分類によると色も異なるらしいが)、ここではその音韻的特徴から「灰色」に軍配が上がる。苦し紛れのこじつけの感がなきにしもあらずではあるが、VIの形容詞の内では、そのうち「灰色い」も普通に使われるようになるかもしれない。
日本語もドイツ語も、グレーあたりで、その形態的ふるまいが区別されるという、文字通り「グレーゾーン」となっている(これはダジャレ)。その点では両言語の間にそれほど違いはないとも思える。
今回は、色彩基本用語の含意の普遍性が、このように複数の言語において、文法的性質に反映していることを示してみた。普遍性という観点から、それぞれの言語において発見があり、説明を付することが可能になる。読者のみなさんの知る言語で色彩語彙はどのようなふるまいを見せるだろうか、一考されたい。
-
- 2021年05月04日 『言語のダイバーシティ 5. 関係節 仁科陽江(広島大学)』
-
5. 関係節
テレビドラマ『ドラゴン桜』の続編の放映が16年ぶりに始まった。低偏差値の落ちこぼれ高校を東大に行ける高校にするために、入試に絶対受かる先生がやってくるという青春ドラマだ。
ここでの「東大に行ける高校」「入試に絶対受かる先生」というのを、英語など外国語に堪能な読者には翻訳してみていただきたい。
「入試に受かる先生が来た」をドイツ人日本語学習者は次のように訳した。
Der Lehrer, der die Aufnahmeprüfung besteht, kam.
いわゆる関係文relative clauseである。「Der Lehrer kam先生が来た」という主節の中の名詞句「der Lehrer先生」に後続して「入試に受かる」が後方より修飾する。ここにコンマで埋め込まれた関係節の下線部derは関係代名詞で、男性・単数・主格という三つのカテゴリーを表す。性と数は主節の中の名詞「Lehrer先生」によって、格は関係節の中のその名詞の格関係によって決まる。すなわち主格は「der Lehrer besteht die Aufnahmeprüfung先生が入試に受かる」という文の主語が先行詞であることを示す。
これが英語であれば、関係代名詞whoは、主節の中の先行詞が有生物であり、関係節の中で主格になることを表す。
つまり「関係」代名詞が「関係」節を導入して、関係節内の格関係や主節との関係を示す標識となっている明晰な構造が見て取れる。
しかしながら、これでは先生が入試に受かるということになってしまう。実際に入試を受けるのは先生でなくて生徒である。本来の日本語の解釈になるためには、「その助けによって durch dessen Hilfe, with whose help」と所有格の関係代名詞を使うとか、「教えてもらえば」と副詞節をつけるなど、なんともまわりくどい表現になってしまう。
渋谷のハチ公についての説明で、「飼っていた人が死んだ犬が毎日ここに来ていた」のような(我々にはごく普通の?)表現に、先ほどのドイツ人日本語学習者は、なんてアクロバティックな構造なんだ、死んだのは人か犬か、などと、理解に頭を抱えるようなのである。
日本語は関係詞を持たない。
被修飾語となる主名詞との関係が明示されないので、「昨日食べたカレー」「昨日食べた客」「昨日食べたレストラン」「昨日食べた箸」は全く同じ構造となり、箸を食べた?とか、人喰い人種?とかいう解釈も不可能ではない。
修飾する節の中では以下のように格関係が格助詞によって示されるが、それが空所gapになることによって関係節化relativizationされる。
昨日(客が)食べた [主格]
昨日(カレーを)食べた [対格]
昨日(レストランで)食べた [場所格]
昨日(箸で)食べた [具格]
昨日(客と)食べた [共格] など
日本語のように関係詞のない空所型の関係節を持つ言語はそれほど多くないようで、たとえばナイジェリア南部で話されるイジョ語が同じ構造をとる。アメリカのスー語族のラコタ語や、メキシコのマヤ語族のユカテコ語も、関係節を後置するが構成原理は同様だ。
空所という考え方を適用するなら、冒頭の不可解な例はもう一つ離れた節に空所があると考えることもできる。
(先生に)教えてもらえば入試に受かる
(犬を)飼っていた人が死んだ
関係詞を用いて節を接続するヨーロッパ言語ではこんなふうに節を越えることはできない。
関係節内の統語機能が標示されない日本語の解釈は、実際には名詞の意味によって常識や文脈で判断するのであろう。「太らないケーキ」と聞けば、普通はケーキを食べると太るのだから、(ケーキを)食べても食べた人が太らないようなケーキであるというふうに、語用論的理解に至る。
非標準的英語では、a cake where you never gain weight.(Comrie 1999)と言えることもあるらしい。ここで関係詞として用いられているwhereは本来場所を表す関係副詞であるが、主名詞と関係節の意味を結ぶ一種のメタファーが作用しているのかもしれない。In whichやon whichから拡張して、with whichやthrough whichという副詞句一般の関係を示しているとも考えられる。
このような関係副詞が、いわばユニバーサルな関係詞として用いられる例がある。
フランスで話されているドイツ語変種のアルザス語では、whereにあたるwo(またはwu)がどんな格関係であろうと関係節に常に出現する。そこでは格関係を示さず、関係詞が接続詞化したと考えて良いだろう。ドイツ語フランケン方言では、この接続詞化したwoに加えて、derとかdasとかの性・数・格を表す関係詞が並置され、独特の機能分化を起こしている。
他方、アルザス語では、関係詞で表せない格関係を、関係節内で具格や共格の前置詞句によって表すことがある。次の例では、「あそこに[私が長い間(彼と)働いた]男が座っている」という文の関係節の中に、主節の「男」を指す代名詞の前置詞句mét-em「彼と」が出現する。
Dèrte sètzt e Mann [wu -n -i lang mét -em gschaft han]
あそこ 座る [3単現] [不定] 男 [関係詞] [与] [1単主] 長い [共] [3単男与] 働く [過分] [助動 1単現]
ここでは、代名詞残留型pronoun retention typeと呼ばれる、ペルシャ語(印欧語族)やキリバス語(オーストロネシア語族)の関係節のタイプと同じことが起きている。次の例では、「私は[ハサンにじゃがいもを与えた]女性を知っている」という関係節の中に、与えた女性を指す代名詞が「残留」している(Comrie 1983)。
man zanirā [ke Hasan be u sibe zamini dād] mišenāsam 私 女性 [対格] [関係詞] ハサン [与格] 彼女 ジャガイモ 与えた 知っている [1人称・単数]
ただし、このペルシャ語の例で関係節の中に残留している代名詞は主格だが、アルザス語では前置詞句として現れる格だけのようである。
上記の日本語の例で「昨日食べた客」が主格とも共格とも解釈できるが、代名詞を残留させないまでも、代名詞と共起しやすい副詞とともに「昨日(その人と)一緒に食べた客」とでもすれば共格であることがわかりやすくなる。これも一種の「残留」のようなもので同じ原理ではないだろうか。
なぜなら、「食べる」と聞いて、人はまず「何を食べたか」「誰が食べたか」と考えやすい。他動詞文でも必須の項である。そこには関係節の作りやすさ、理解しやすさ、という認知的な原理が存在すると考えられる。
Keenan & Comrie (1977)は世界の諸言語の関係節を調べることで、主名詞の関係節で担う統語機能と関係節の作りやすさを接近可能性階層accessibility hierarchyとして提示した。そこでは主語である場合に最も関係節が形成されやすく、主語>直接目的語>間接目的語>斜格の順で、階層の下位に行くほど関係節が形成されにくい。
マダガスカルの言語マラガシでは、主名詞の関係節での統語機能が階層において最も高い主語である場合にしか関係節を作れない。
おなじオーストロネシア語族のインドネシア語において、目的格の関係節「監督が受け取る給料」をそのまま関係節にすると、以下にある*のついた例のように非文法的になり、主名詞との格関係を主格にするために関係節を受け身にする必要がある。
次の例では、yangはそれ自体格関係を示さない関係詞、menetima「受け取る」という動詞に受け身の派生辞di-をつけることで、主名詞Gaji「給料」が関係節で受け身文の主語の機能を担うこととなり、文法的に可能になるわけである。
*Gaji [yang sutradara menetima] itu
Gaji [yang di-terima sutradara]itu
アルザス語の代名詞残留が前置詞句として現れた具格や共格という「斜格」は、階層の最も下に位置する。斜格に属する受益格benefactiveなども同様の振る舞いをする。
「斜格」のレベルもより細分化することは可能で、場所格in whichや奪格from whichは比較的関係節を形成しやすいが、比較格*than whichになると、英語では関係節にならない。
Keenan & Comrie 1977は、同じ言語においても、階層の下位の統語機能を持つ名詞句で関係節が形成できれば、そこよりも上位の全ての名詞句でも関係節が形成できるという含意implicationの普遍性を示した。
アルザス語では、斜格における代名詞残留に加えて、他にも機能的な分け目が存在する。主語や直接目的語という上位の名詞句を関係節化する場合は、関係詞woに、与格を表す-inがつかない。階層の下位になるほど、複雑な手続きをしなければいけなくなることがわかる。
このような階層上の振る舞いの違いは、階層のある位置で区別されることが、そこから上位の機能を持つ名詞句全てにおいて同様になされるという含意の普遍性を反映するものである。
以上、関係節の多様なあり方に触れ、通言語的な普遍性も紹介した。
このようなことを考え合わせると、冒頭の例で学習者がまず主格の関係だと考えたのは、ある意味でもっともだとも言える。人の認知のあり方として自然であることは、世界の言語の調査によって明らかにされたようなものだ。階層の下位になるほど複雑な構造になることをみたが、「入試に受かる先生」という関係節は、背後にはいろいろな意味を抱えながらも構造自体は単純である。このスッキリ感に騙された可哀想な学習者の間違いをちょっと正当化して、今回は終えることにする。
-
- 2021年04月27日 『言語のダイバーシティ 4. 類像性と日本手話 仁科陽江(広島大学)』
-
4. 類像性と日本手話
言語記号は恣意的である、とは近代言語学の祖と言われるソシュールのことばである。言語学の最初の授業で聞くこともあるだろう。机が「机」と呼ばれるのに理由はない。それが証拠に英語ではdeskと呼び、他の言語でもそれぞれである。
それを恣意性というが、実際には言語に恣意的と言えない特徴もある。
オノマトペは実際の音を模倣しているし、言語によっては名詞の重複が複数、動詞の反復が反復動作を表したりする。実際の時間軸に沿った語順や条件節の先行など、統語的にも形式と意味になんらかのつながりが見出される場合もある。
それは類像性あるいは図像性iconicityと呼ばれ、音声言語にもある傾向だし、手話では視覚的に表される。手話言語は、その類像性ゆえに、ジェスチャーと混同されたりして誤解されることも多い。
言語のダイバーシティについて語る時に、音声言語とは異なるメディアを持ち、独自の文法をもつ言語として、手話言語を語らないわけにはいかない。同時に、手話が言語である以上、母語話者native signerが存在し、生産的で複雑な体系をもつことは音声言語に匹敵する。世界には様々な手話言語が存在し、日本国内にも日本手話のほか、様々な方言や、年齢などの位相によるバリエーションが見られる。
音声言語が時間に沿って発話を継起させる線状的なものであるのに対し、手話言語は空間的な同時性を持つ。手の形、向き、位置、動きなどが組み合わされ、我々が音韻で意味を区別しているように、弁別性をもった表現が可能になる。
手話といっても手だけで表現するわけではない。顔の表情や目、口などの部位の動き、頭や体の向きなどの非手指表現は重要な役割を担う。
前回扱った類別動詞のような働きが、日本手話にも見られる。その類像性は、形状や大きさや距離を目に見える形で表すことができ、対象を区別する。
ものを「置く」場合には、英語ではputで済むところだが、それを縦に置くのか横に置くのか、あるいは一つ置くのか複数かによって、区別する。
「食べる」という動詞は、その対象によって表現が異なる。お箸でラーメンを食べる場合、手でパンを食べる場合、スプーンでカレーを食べる場合などで使い分ける。
日本語では「行く」という動詞は場所の移動を表すだけで、移動の方法を表すためには「車で」「歩いて」など、副詞句などを補う必要があるが、日本手話ではその移動方法も図像化することが可能である。
もちろん音声言語でも語彙によってある程度区別できる例はある。ドイツ語では「置く」場合にstellenかlegenを選ぶ必要があって、縦か横かぐらいの区別はできる。
英語のgoにあたるドイツ語のgehenはその移動の様態としては歩いて行くことに特化される。方言にもよるが、走る場合はlaufenやrennen、自転車を含む車両ではfahren、飛行機で行くならばfliegenという具合だ。これが日本手話では、自転車や自動車や新幹線の区別をし、千鳥足などの歩き方まで表現できるわけだ。
そしてそれはあくまで一次的な表現なので、日本手話の「新幹線」と、ドイツ語のfahrenと日本語で「行く」とだけ言うのとが、同じレベルにある。「新幹線」の手話を、「新幹線で東京へ行った」とかmit dem Shinkansen fahrenに対応させると、飛行機でなくて新幹線で、といったニュアンスが付加されてしまう。だから、fahrenを「乗り物に乗って行く」と日本語に訳したり、「新幹線」で移動を表す日本手話をmit dem Shinkansen fahrenとドイツ語に訳したりする必要はないわけだ。
この例において、移動動詞としてどれだけの類像的意味が込められているかは、日本手話>ドイツ語>日本語の順で、連続的であることがわかる。
類別詞や類別動詞の選択は、その時の状態によって一定でないことが報告されている(Serzisko 1980)。それには類像性が作用していると考えられるが、定着したと思われる日本手話の語彙にもそのようなことがある。
「洗濯する」に相当する手話単語は、両手でもみ洗いするような動きをするが、「夜遅く洗濯してうるさいと隣人に言われた」という時に、日本手話の辞書にある単語を使って訳した筆者は、ろう者から洗濯機がまわるような動作に直されたことがある。音のしない手洗いと洗濯機の騒音とが意味的に競合するということであろうか、
「洗濯機」という語をインターネットの手話辞典や動画で調べると、両手でもみ洗いする動作に指文字の「き」をつけて表している。このような語形成は日本手話に多いけれども、そしてそれは生産的ではあるのだけれども、なんだか聴者の日本語話者の発想のようだ。そもそも「洗濯機」という語自体が日本語からの借用語である。
日本手話には興味深い表現体系が数多くある。ダイクシスやヴォイス、自動詞・他動詞など、言語学の一見難しそうな概念について、手話を例にして視覚化して説明できることがあり、筆者は言語学の授業でよく使わせてもらっている。
たとえば、「今」「ここ」「私」といった発話場面に依存する時間・場所・人称を指示するダイクシスというのが、日本手話では文字通り体現されている。話者の体自体がダイクシスの中心としての発話時点であり、体の前は「明日」「来週」などの未来、体の後ろは過去を表す。人称のダイクシスについても話者の体が常に1人称であれば、自ずと動作の方向が決まる。
類像的なのは語彙だけでなく、日本手話の文法にも現れる。
語彙のつなぎ方、頷きなどの頭の向き、目の開き方や口の形など、それで文法を説明できるような表現方法を、ろう者の母語話者は駆使している。
手の形・向き・位置・動きの組み合わせで弁別性が形成されたように、眉の上げ下げや目の開き方や顎の位置などの非手指要素の組み合わせによって、数多くの区別が文法的になされることわかっている。
「先生」「車」「破壊」と手話単語を並べるだけでは、先生が車を壊したのか、先生の車が壊れたのか、あるいは先生の車を誰かが壊したのか、わからない。先生が車を壊したとしても、不注意で壊してしまったのか、意図してわざと壊したのか、ここでも解釈は別れる。そこでの意味を決定づけるのが非手指表現である。
「先生の車」という名詞句においては、「先生が」で現れるような頷きがなく、「先生」と「車」がひと続きに表現される。他動詞と自動詞は主語を指さしで示すことによって区別されるし、唇を一文字に結ぶような口型によって動作主のコントロールを表し、他動詞に解釈されることもあるだろう。非意図的である場合には眉を上げずに目を大きく開く(木村・市田2014: 33, 40)。
このようなことは、たとえばロシア語のような屈折のある言語であれば、名詞の属格や主格という格変化や、主語となる人称の性や数による動詞の一致などで区別する。日本語では動詞に「壊れる」「壊す」という自動詞・他動詞の区別があるし、「の」や「が」という格助詞もあり、補助動詞を付加して「壊してしまった」などと表すこともできる。それぞれの言語においてこれらが文法事項であるように、非手指表現は日本手話の文法標識となるのである。
そのように重要な文法なのであるが、ともすれば自分の母語である日本語に手話単語を添えるだけの学習者には、なかなか伝わりにくい。手話使用者である中途失聴者の母語も日本語である。上記で借用のことを少し述べたが、日本語というマジョリティの環境下にある日本手話は、言語接触による混成的な性質もその特徴としている。
ろう者もまた、フォリナートークやティーチャートークと呼ばれるような、母語話者がその言語に習熟していない人に配慮した話し方、日本語話者にはわかりやすいが、本来の彼らの日本手話とは異なる不自然な手話を使うこともよくあるのではないか。
日本には日本語以外に、アイヌ語や琉球諸語、そして日本手話という、少数言語が存在する。
世界には何千という言語が存在するが、絶滅の危機にさらされている言語は少なからずある。ネイティブサイナーと呼ばれる母語話者の少ない日本手話が、絶滅に瀕した危機言語とならないために、日本手話の文法記述は喫緊の課題だと筆者は考えている。
少数言語話者としてのろう者は、独自の言語を持つように独自の文化ももつ。ダイバーシティ&インクルージョンが語られる昨今、日本手話研究の進展は、言語の多様性を端的に示して理解を促進し、言語のみならずダイバーシティを重んじる日本社会のために非常に意義があると、筆者は期待している。
-
- 2021年04月20日 『言語のダイバーシティ 3. 類別詞 仁科陽江(広島大学)』
-
3. 類別詞
前回は文法上の性について、名詞のクラスや文法的一致などの話をしたが、では、日本語はどうなのだろうか。名詞となる対象を分類しようする現象はどの言語にもあり、その体系が文法と密接に関わっているという記述から、考えを巡らしてくださった読者もあったかと思う。
ヨーロッパ言語の学習者が文法上の性で苦労するように、ヨーロッパの日本語学習者にとって日本語のものの数え方は驚きである。Two pens、two books、two cars … のtwoが日本語では2本、2冊、2台… というように、数詞にそれぞれの類別詞classifierをつけなければならない。学校文法では助数詞と呼んでいるが、数詞とともに数える場合に名詞を類別するので、類別詞の一種numeral classifierと見なすことができる。
この分類はある程度説明することができる。ペンのように長細いものは「本」、平たく厚みのないものは「枚」、それを綴じたものは「冊」、機械類は「台」など、ものの形状や用途によって分類するので理解しやすい。
これらの無生物に対して、人間「人」、四つ足の動物「匹」や「頭」、鳥「羽」などといった有生物の区別も自明である。
細かい分類は数多くあって、数百ともいわれており、日本語の類別詞は一体いくつあるんだ、と学習者からよく問われたものであったが、教育現場では、限られた数の使用頻度の高いもので間に合わせているのが実情だろう。
ものの形状によって類別詞が決まるとはいっても、形が見えないものはたくさんある。以下の例で、日本語話者が皆同様に「本」を用いるのはなぜだろうか。
電話一本よこさない。
今シーズン三本目のホームラン
映画の二本立て
これは一本とられた。
論文を一本書いた。
今でこそ電話もワイヤレスだが、相手と繋ぐ電話線、ホームランの球の軌跡、映画のリールなど、長細いもののイメージだろうか。「立てる」からの連想かもしれない。一本とられた、というのは、柔道からの転用であろう。柔道の一本はたとえば背負い投げなどの動きの軌跡も思わせる。論文や小説を一本と呼ぶのはかつて巻紙に書いていたのでそう呼んでいたのかもしれないが、今では何か完成したもの、やりとげたものというイメージもある。それは柔道の一本、ヒットやホームランなどとも共通する。ファウルは一本といいにくいのではないだろうか。などなど、なんとか理由づけができそうであるが、これらは筆者の想像や感覚であって読者の皆さんと共有できるかどうか。
いずれにせよ、具体的な形状を示す類別詞が、より抽象的なものに拡張されて使用されていることは見てとれる。
そんなところにも、使用頻度の高い類別詞で「間に合っている」理由があるといえるだろう。
日本古来の和語による数え方もいろいろあって、箪笥はひとさお、蚊帳はひとはり、など、現代の我々にわからなくなりつつあるものも多い。
他方、「ひとり」と「ひとつ」は有生物(人間)と無生物を大きく分けるもので、日本語教育でも初めに習う数え方である。このような分け方は、たとえばベトナム語もcon(有生物)とcá(無生物)という対立をもつ。
ただし日本語では、人は3人以上、物は11以上で漢語に替わってしまい、わずかに方言では四人「よたり」「よったり」などが残るのみである。
言語は常に変化しているので、類別詞の使い方が変わることもある。
若い人たちが「私の1コ上」と言って年上のことを表しているのを聞いて、筆者のような前時代話者は、「個」はここまで拡張されたか、と思ったものだ。しかし、それほど生産的でなく、学生たちは年齢というより学年の単位として使っているようでもあるし、年齢を意味するとしても、二桁以上になると言いにくいそうだ。個人差はあるだろうけれども、15とか20とかキリのいい数字なら「20コ上」と言えるという若者もいて、なかなか奥が深い。
類別詞は、その語源を比較的たどりやすいのも特徴的である。たとえばインドネシア語では、丸くて小さいものを「〜粒」と数えるときのbijiは「種」、果物や丸い無生物を「〜個」と数えるときのbuahは「果物」というそれぞれの意味に由来する。日本語で人を「〜人」と数えるように、人をあらわす名詞orangを類別詞に使用している。ちなみに、この言語では名詞を重ねて複数を表すので、「三人の人three persons」は3-orang orang-orangという理屈になる。が、実際にはそこまで重ねない方がふつうらしい。3-orangと言う時点で複数であることはわかるので、言わなくてもわかることは言わないというわけである。(これがヨーロッパの言語では、3であれば複数を言語化しなければならない、という逆の論理になる。)
このような類別詞をもつ言語は、アジアをはじめ、地理的にも系統的にも関連なく世界に散在する。そして、有生性、形状や用途・機能などによる類別が見られることも共通している。
類別詞は、a piece of paperのような物質名詞に数える単位を与える場合とは区別すべきで、可算名詞の単位付けとしての類別詞のことであり、名詞の意味的分類をあらわす言語手段である。
そのような類別詞を持つ類別詞言語classifier languagesの話者の数の捉え方は、ヨーロッパ言語など非類別詞言語non-classifier languagesのそれと異なるのではないかという考えもあり得る。
「学生」と日本語でいうと、人は集合体のように、ある概念のように認識していて、個体として見ていないのかもしれない。だから、前回扱ったドイツ語のようにいちいち男女や複数の区別をしなくてもよい。そして対象を個別化するときには、類別詞を用いて数えれば良いことになる。
「犬は忠実だ」というときには総称としての犬を指して、犬というものは忠実であることを意味するが、「犬がほえた」というときは、ある特定の犬がほえたという事実として解釈されるであろう。それは単数であれ複数であれ個体を指す。
この違いを、たとえばベトナム語では類別詞を付加するかしないか(chó とcon chó)で表すことができる。
類別詞は数詞とともに用いられるばかりではない。
中国語では指示代名詞とともに、日本語のように「この3冊の本」と、類別詞(中国語文法の用語では量詞と呼ばれる)「本」を用いて表すが(这三本书)、この場合の近称指示代名詞「这」は数詞がなくても類別詞と共起する(这本书「この本」)。
ベトナム語では(数詞)+類別詞+名詞+(修飾句:形容詞や指示詞)という構造をもち、( )部分は省略できる。たとえば「この犬」というときにcon chó này(類別詞「匹」+「犬」+指示詞「この」)として、特定の犬を指す。
これらの言語で類別詞は、数のカテゴリーの表現に必須であり、また、対象を限定したり個別化したりする働きを持っている。
類別詞の行う名詞の類別を、動詞classificatory verbで行う言語もある。日本語では名詞が有生物か無生物かで存在動詞を「いる」と「ある」で区別するぐらいのことはするが、ものの形状や機能によって動詞を使い分ける体系はない。
アメリカ合衆国南西部の原住民の言語、ナバホ語には、丸くて小さいもの、細くて固いもの、平たくて曲がるもの、容器に入ったもの…といったように、その形状や状態によって10余りの動詞語幹がある。そのそれぞれが、「ある」「運ぶ」「投げる」など、主にものの動きを表す動詞の意味によって、区別される。「これ、あげます」と言ってプレゼントをわたすとき、どんなプレゼントかによって「あげる」を表す動詞の形態が異なるわけだ。
このようにしてできる多くの組み合わせのうち、有生物を投げるのと、長くて固いものを投げるのとが同じ形になるのは、偶然というよりも、「投げる」という行為によって有生物は物のように扱われているということによる語形融合だろうか。
ナバホ語の次の三つの文はすべて「お金がある」ことを表す。
(1)sì -ʼą́「お金(硬貨)がある」
(2)sì -nil「お金(硬貨の山)がある」
(3)sì -ł-tsooz「お金(紙幣)がある」 (Barron 1980:18)
動詞語幹-ʼą́、-nil、-ł-tsoozはそれぞれ、丸くて固いもの(例1)、量のあるもの(例2)、平たくて曲がるもの(例3)という形状・状態によって「お金」を類別する。対象物の形状を動詞によって表すという一種の統語的な手続きをとっている点で、ベトナム語や中国語のような名詞句の中でのみコード化される類別詞と異なっている。
これまでの連載で、名詞分類のあり方がいかに多様であるか、インドヨーロッパ語族の言語に特徴的な文法上の性gender、スワヒリ語やジルバル語のような名詞クラスnoun class、日本語やベトナム語などがもつ(数量)類別詞classifier、それにナバホ語の類別動詞classificatory verbを例に見てきた。その表現手段は、名詞内部で音韻的特徴や語形成によってなされているものから、固有の言語要素を名詞に付加したり並列させたりしたもの、名詞を離れて動詞語幹に表されているものまで、さまざまである。そこには形態論のレベルから統語論のレベルへの広がりもみられる。
また、これらが文法に直結したところで使用される際に、逸脱や、ゆれや、拡張があったりするところにも、生きた言語の姿を見ていただけたのではないかと思う。
類別詞や類別動詞が行なっているような、ものの形などを言語化して表すことは、類像性の高い手話言語にとっては重要な表現手段となる。というわけで、次回は手話のお話。
-
- 2021年04月13日 『言語のダイバーシティ 2. 文法上の性について 仁科陽江(広島大学)』
-
2. 文法上の性について
第二外国語でドイツ語やフランス語などを選択した学生がまず驚くのが、名詞に性があることだ。Vater「父」が男性名詞でMutter「母」が女性名詞というのは、まあ、わかる。イタリア語やスペイン語になると、語尾の母音で性別が区別できることが多く、イタリア語でおじいさんがnonnoという男性名詞でおばあさんがnonnaという女性名詞、おじさんがzioでおばさんがzia、息子がfiglioで娘がfiglia、その二人がイケメンと美女であれば、figlio belloとfiglia bella・・・といった具合に、男女の形がきれいな対立をなすのは学習者にとっては嬉しいところだ。
しかし、「手」や「机」や「法律」や「健康」など、すべての単語が男性か女性が、はたまた中性かどうかを覚えなくてはならない。フランス語で「太陽」が男性、「月」が女性であるのに、ドイツ語では逆だ。「家」はロシア語では男性、フランス語では女性、ドイツ語では中性だ。どうしてそうなのか説明がつかない。上記のイタリア語の例から男性名詞はoで終わると思ったら、女性名詞mano「手」のような例外もある。
「先生、なんとかならないんですか」とドイツ語を履修した学生が泣きついてくるので、思いつくまま、役に立ちそうなことを言ってみる。
「ドイツ」や「日本」のような国の名前はたいてい中性だ。(が、イランは男性、スイスは女性。)ワインもウイスキーもブランデーも、お酒はたいてい男性だ。(が、ビールは中性。ドイツの代表的なお酒なのに。)
このカッコづけのところで学生ががっかりするので、文法上の性は意味で決まっていないことを言ってみる。
Mann「男」が男性名詞でFrau「女」が女性名詞であるのに対してMädchen「少女」が中性なのは、少女が成熟していないからなどではなく、もともとMagdに縮小辞-chenがついたもので、逆に言えば、縮小辞-chenや-leinのついた名詞はすべて中性名詞だと断定できる。
Gesundheit「健康」やFreundschaft「友情」のような抽象名詞が女性名詞であることは多いが、-heitや-schaftの語尾があるものはすべて女性名詞である。このように、意味からでなく形式から判断できるものがある。
それでも不満そうな顔をしている学生には、「ドイツ語は三つで済むけど、四つ、五つ・・・1ダース以上になる言語もあるよ」と言って慰める。
George Lakoffの著作 Women, Fire, and Dangerous Things(邦訳あり)は、そのタイトルをオーストラリアの原住民の言語であるジルバル語の、言うなれば女性名詞に属する構成要素の特徴からつけたもので、この言語の名詞が四つのクラスにカテゴリー化されるあり方を論考している。女性を中心にした名詞のクラスに対し、男性を中心にした動物を含めたクラス、この二つが人間を中心にしているのに対して三つ目のクラスは食用植物、四つ目のクラスはそのどれにも入らない残りである。四つぐらいなら、男性、女性、中性、その他、と拡張して、ヨーロッパ言語にあるような文法上の性との比較に値する。
日本語で「性」と呼んでいるのも話をややこしくする。ドイツ語では一般的に性をあらわすゲルマン系の語Geschlechtに加えて、文法上の性をGenus、生物学的な性をsexus, 社会的な性をGender(外来語ではあるがゲンダーとも読む)と区別しており、ラテン語のGenusはフランス語のgenre「文法上の性、ジェンダー、種」と同根で、外来語としてジャンルと我々が呼ぶように、「グループ分けしたもの」ぐらいの意味である。大きく見れば、文法上の性とは、分類された名詞のクラスのことに他ならない。
スワヒリ語には、数え方にもよるが名詞のクラスが18あり、それぞれのクラスは、「人間」「木」「果物」「道具」など、中心的意味による分類も可能であるが、クラスを標示する形態が特徴的である。
以下の文で、「カゴ」「大きい」「1」「落ちた」というすべての要素に接頭辞ki-がついて、カゴが「道具のクラス」であることを標示している。
Kikapu kikubwa kimoja kilianguka 「一つの大きなカゴが落ちた。」
これが複数になると、別の名詞クラスを形成し、接頭辞ki-がvi-になる。
Vikapu vikubwa vitatu vilianguka 「三つの大きなカゴが落ちた。」
これらはわかりやすい例で、実際には名詞と動詞の接頭辞が同じ形でないことの方が多いが、いずれにせよ、クラス標示をそこで行っており、たとえ接頭辞のない名詞でも動詞の接頭辞がその名詞のクラスを標示する。
このように、言語は異なってもそれぞれのやり方で名詞が分類され、文法体系に組み込まれている。
では、他言語からの借用の場合はどのように分類されるのだろうか。新しい言葉が参入したときに、これは男性名詞、と決める誰か偉い人がいるわけではない。ドイツ語のように、なぜその言葉が男性名詞なのか説明できないような分類であっても、母語話者は、多少の「ゆれ」を除き、たいてい共通して同じ性にしてしまうから不思議だ。
二つの言語の間のことなので、由来する言語での性をそのまま受容するか、既存の類義語の性に準ずるかどちらかということになる。その際、あまり使われておらず元の発音が残っているような場合は前者、発音がドイツ語化してよく使われている場合は後者である傾向もある(Drosdowski 1984:209)。そのため歴史の流れの中で性が変わるものもあり、方言にその名残をみることもできる。
文法上の性を持たない英語からの外来語、たとえばT-Shirtなどは、ドイツ語のシャツを表すHemdが中性なので、類推によって既存の上位語の性が用いられるのだと考えられる。
また、ドイツ語にはeで終わる女性名詞が多いので、フランス語のbagageやcigareは男性名詞なのに、ドイツ語になると女性名詞である。スワヒリ語では、アラビア語の借用で「本」を表すkitabのkiが接頭辞と認識されて、複数のクラスではvitabとなったり、同じくアラビア語の「先生」を表すmu’allimも、単数接頭辞m-をもつ「人間」のクラスに取り入れられて、複数形の形がwalimuとなったりする。もとの語の音韻的特徴によって受容の際の名詞クラスが決まる例である。
さて、スワヒリ語では動詞の不定詞も一つの独立したクラスを成している。
前回、ジェンダーと言語を扱ったが、ドイツ語の動詞から派生した分詞を用いてジェンダー差をなくそうとする動きがある。Student「学生」の代わりにStudierende、Lehrling「弟子」の代わりにAuszubildende、というふうに動詞の現在分詞をもちいて、それぞれ「勉強する人」「職業教育を受ける人」と名詞化するわけである。
ジェンダーについてこれまで問題視されてきたのは、男性形だけが用いられ女性形に欠けること、また、一般化する場合に用いる不定の代名詞jeder, man, werなども、文法的にはすべて男性名詞の振る舞いをすることであった。そこで、たとえば動詞studierenの現在分詞studierendを名詞的に用いて、Jeder Student「各学生」をalle Studierende「全学生」と言い換えれば、男性形を使わなくても良いし、男女両方を併記したり*や_をつけたりといった煩雑なこともしなくてよい。
しかし、この現在分詞がどちらの性を指すのかを知る方法は(単数である限り)ある。「ある学生の冒険」という小説の題名Abenteuer eines Studierendenでは、einesという冠詞の男性単数属格によって、この学生が男性であることを示している。女性であれば、Studierendenは確かに変わらないが、冠詞の女性単数属格einerをとらなければならない。
ある名詞の性を決めるのは、文法的一致である。その原理は、スワヒリ語の数詞や形容詞、動詞の接頭辞体系においても同様にみられる。ジルバル語にも名詞と共起する指示代名詞のような名詞マーカーが四種あり、文の中の役割によって形を変えたりしながらその名詞の所属するクラスを標示している。
もっと具体的に言えば、ドイツ語のMann「男」は指示対象が生物学的に男だからでも、男性名詞の固有の意味をもつからでもなく、たとえば、eine kluge Mannでなくてein kluger Mannと言うから男性名詞なのである。イタリア語のmanoがoで終わっていてもuna mano piccolaと言うから女性名詞なのである。すなわち、Mannやmanoを修飾する形容詞の屈折語尾や不定冠詞の形がその名詞の性を決めている、というわけである。ロシア語では、動詞の過去形の語尾で、その主語の性がわかる。このことは、文法的な一致が必要な要素すべてにおいて作用する。
つまり、名詞の性を決めるのは、名詞以外のものなのである。
不定の人称代名詞は文法的には男性名詞であり、屈折語尾や所有代名詞もその性に準ずるので、「誰も皆その妊娠の体験が異なる」という意味のJeder erlebt seine Schwangerschaft anders (Genzmer 1995: 327)という文を見て、文法的には全く正しいのであるが、「男が妊娠したのか!」と、つい思ってしまうのは筆者だけではないだろう。また、Mädchen「少女」など中性名詞であっても所有格は男性名詞と同じ形であり、それを現実に合わせて所有代名詞ihr「彼女の」を用いると非文法的な文になってしまう。要するに、現実の指示対象referentの性sexが問題なのではなく、それを表す語彙の文法的な性genderが文法的一致agreementという制約をもち、文を形成する必須要素になっているというわけである。
このことについて、実は面白い現象があることを最後に言っておきたい。
Es war ein/*eine schönes/*schöne Mädchen, das/*die ich nie gesehen hatte, es/sie hat ・・・「それは私が会ったことのない美しい少女で、彼女は・・・」
Mädchenは中性であるので、アステリスクのついた女性形が非文であるように、冠詞や形容詞の付加語や関係代名詞など、名詞句内にある限りは文法的な逸脱を起こすことはない。が、その境界を超えて、先行する名詞を指すときには、中性人称代名詞esの代わりに女性人称代名詞sieが使われて不自然ではない。ドイツ人に尋ねれば、それは非文法的だ、と言うだろうが、実際に彼らは会話の中でそうやっている。指示対象である現実の女の人を思い浮かべて発話することがあるということだろう。
このような境界では話者も一息ついてポーズが入ることも多い。喉元過ぎれば(文法)性を忘れる、とでも言っておこう。
さらに言えば、その「喉元」は言語によって異なるようである。
フランス語では述語になる形容詞や分詞も主語の性に従って屈折する。抽象名詞majestéは女性名詞で、大文字で所有代名詞とともに男性君主の称号Sa Majesté「陛下」となる。述語形容詞は女性形になるが、節をまたいで人称代名詞になると、やはり男性形になる例が報告されている(Sa Majesté fut inquiète, et il….)。一方、スペイン語では、付加語用法の形容詞は名詞と同じ女性形(Su Majestad suprema)、述語用法の形容詞は男性形(Su Majestad está contento)となる。人称代名詞が男性形となるのは、ドイツ語やフランス語と同じ現象である。
ということは、付加語・述語・関係詞・人称代名詞とあるなかで、ドイツ語やフランス語の「喉元」は人称代名詞の前、スペイン語は述語の前に位置することになる。これらの間にある階層が見えてくる。
付加語 > 述語 > 関係詞 > 人称代名詞
階層の左にいくほど名詞の文法上の性に忠実であり、右に行くほど現実の指示対象の性を指向しやすくなるという仮説が立つ。述語と関係詞の順番については、これをサポートするロシア語やセルボクロアチア語の例が報告されている。(Corbett 1991:231f)
この階層は、文法的一致が必須である名詞への統語的な近さの違いと言ってもよいかもしれない。名詞の文法上の性と指示対象の生物学的性を区別する点を「喉元」と喩えて、それが言語によって異なることを示したが、その異なり方が階層で示されたような一定の原理に沿っているところは、どんな言語でも同じである可能性がある。
性を含めて名詞クラスの様々なあり方の片鱗を見たが、名詞となる対象を分類しようとする現象はどの言語にもあり、その体系が文法と密接に関わっていることも共通する。
「言語のダイバーシティ(多様性)」という連載であるが、それに表裏一体をなすものとして「言語のユニバーサリティ(普遍性)」とでもいうことが、早くも感じられることになったが、それについてはまた、別の回に。
-
- 2021年04月06日 『言語のダイバーシティ 1. ジェンダーと言語 仁科陽江(広島大学)』
-
1. ジェンダーと言語
「言語のダイバーシティ」というタイトルは、言語の「多様性」、つまり世界にはいろいろな言語があり、日本語話者である我々が知らない多様な構造やしくみがあることを、連載の中で具体的に見てみようという意図からつけたものである。
Linguistic diversityというと、世界中で絶滅の危機に瀕している言語のことや多言語が共存している状態の文脈で用いられることも多いし、我々の身近にある言語、地域の方言や若者言葉、共生する外国人の母語、聴覚障害者の手話などを考える上でも関連する概念である。
ただし、日本語でダイバーシティとカタカナで表すとき、人間社会での多様性、つまり男女の性差、性指向や性自認、年齢、国籍、人種、宗教、障害の有無、あるいは価値観などの違いを認め合う意味で用いられている。なかでも男女共同参画の一環で、ジェンダーの問題として語られることが多い。このジェンダーもカタカナ語としては社会的な性のことを意味し、言語における文法上の性であるgenderや生物学的な性であるsexとは別物と考えるべきである。文法上の性については次の連載で述べることにする。
世界経済フォーラム(WEF)が3月31日、各国における男女格差を比較した最新の報告書を発表した。日本の「ジェンダーギャップ指数」は、調査対象国153カ国中120位と、先進国では最低水準となっている。バイデン政権になって順位を30位にまで上げたアメリカに比べて、日本ではとくに政治経済の分野の女性の進出が劣っている。男女平等を謳う五輪の精神に反する女性蔑視発言に全世界から批判が集まり、東京五輪組織委員会会長が辞任したことも記憶に新しい。この元首相は自分の偏見に向き合うことのないまま謝罪会見の場で逆ギレし、ジェンダーに対する意識の低さを露呈した。
皆さんには、以下のクイズを解いてみてほしい。
父親と息子が交通事故に遭い、二人とも大けがをした。救急車で別々の病院に運ばれ、息子の方を担当した外科医は顔を見るや否や叫んだ。「これは私の息子です!」。一体どういうことか。(朝日新聞2021年2月13日「天声人語」より)
答えがわからない人は、外科医は男性であると思い込んでいるのだろう。外科医はお母さんだったのである。人は多かれ少なかれこのような「無意識の偏見」を持っている。女性活躍推進法や男女共同参画基本計画など、法律や制度の整備を進めても、まだまだ一人ひとりの意識啓発が必要なのである。
上記のジェンダーギャップ指数を、政治経済の制度や水準が日本と似ているG7諸国で比べると、11位にあるドイツが最も高い。しかし、1970年代までの西ドイツでは、女性が職に就くためには夫の署名が必要だったという、まさに男尊女卑のような制度が温存していた。現在では15年来の女性の首相メルケル氏のリーダーシップのもと、政治における女性の参画も進んでいる。日本とドイツの違いはどこにあるのだろうか。
それには様々な要因があろうから、その答えはここではすぐに出せないが、ドイツ語使用者の男女平等の意識が言語行動の変容に結びついたことは歴史的にみてとれる。
筆者がまだうら若き(?)頃、実家に出入りする呉服屋や縁談を持ってくる仲人達を尻目に単身ドイツに渡ってから、かの地でよく「日本の女性は解放されているか」と、訊かれた。女性解放を意味するEmanzipationというドイツ語を初めて聞いた。フェミニストと呼ばれる人たちは、女性が解放されるためには言語から変えなければ、と主張して、欧米では70年代ごろから様々な改革が提唱され、男女を差別すると考えられた表現を避けたり言い換えたりすることを意識して行うようになる。
ドイツ語の敬称には、男性はHerr、既婚女性はFrau、未婚女性はFräuleinという、男女を婚姻のあるなしで区別する非対称のパラダイムがあるが、筆者がドイツへ行った80年代後半、未婚であり(しつこいようだが)うら若き筆者に向かってFräulein Nishinaと呼ぶ人は一人もいなかった。
女性を表現する名詞は、男性形に接尾辞-inを付けて女性形が作られる。英語ではactor – actress のようにごく一部の名詞に派生の対立があるにすぎないが、ドイツ語では、女性形が外来語として借用されたなどの場合でない限り、ほぼ規則的に-inの派生語尾をつけて女性形が作られる。Doktor (英語のdoctor)もDoktorin 「博士」となる。ちなみに、上記の外科医のクイズはドイツ語では成り立たない。男性の外科医はChirurug、女性ならChiruruginと、解答がすでに問題文で言語化されているのだから。
この派生の現象は、男性形がもとの形であり、標準であることが前提になる。有標性markednessの概念を借りれば、この対立する言語的単位において、男性形がより一般的で無標unmarked、構造上の手続きがより複雑になる女性形が有標markedということになる。
また、それぞれに複数形があり、男性単数Student、女性単数Studentinに対して、男性複数Studenten、女性複数Studentinnenというふうに、接尾辞-(n)nenがつく。男性と女性が混ざっている場合の複数形はStudenten、つまり男性複数形を用いると文法書にはある。が、それでは女性の存在が見えなくなるというわけで、Studentinnen und Studentenと、両方並べるほか、Student(innen)、Student/innen、StudentInnen、Student*innenなど、女性形を見える化する工夫がいろいろなされてきた。なかでも、ライプチヒ大学はラディカルな改革を行い、学内の言語使用においては、たとえ男性を指すときでもすべて女性形を使用することを公式に決定し、学則も書き換えた(Grundordnung der Universität Leipzig vom 6. August 2013)。
ということは、有標である女性形を無標のように使うことを決めたわけだ。さすがにこれはドイツ全土のドイツ語を変えるまでにはいたっていない。が、両方の性を併記するということは浸透しており、たとえばビーレフェルト大学は、公文書でよく使われるようになった*の使用についてのガイドラインを示している(女性派生形や複数形のほか、形容詞の屈折語尾liebe*r、冠詞の併記der*dieやein*e、人称代名詞の併記er*sieやjede*n、所有代名詞の併記sein*ihrなど)。さらに、ハーゲン通信大学のSteffen Hermanは、性自認は男女に二分されるわけではないとして、男女の区別を超えることを可視化する意味を込めてStudent_inのようにアンダーラインで結ぶことも提唱している(Hermann 2003)。
男性名詞からの派生ということ自体が、男性が主で女性が従属的なイメージにつながるとして、言い換えも行われた。Kaufmann「商人」(「買う」の動詞語幹+「男」)の女性形Kaufmänninに代えてKauffrauと、複合要素Mann「男」をFrau「女」におきかえる、また、男性複数形のKaufmännerをKaufleuteとして、性別のない複数を表す語Leute「人々」におきかえる、などである。
女性名詞から男性名詞への派生という逆のパターンは、極めて珍しい。Witwer「寡夫」はWitwe「寡婦」から派生したそうだが、Hebamme「助産婦」(「とりあげる」の動詞語幹+「乳母」)に対応する派生形は無い。上記のKauffrauの置き換えのような、Amme「乳母」に代わる男性を表す名詞もない。実際に男性を表す場合には、männliche Hebammeと、男を意味する形容詞をつけたり、EntbindungspflegerとかGeburtshelferとか、全く別の語彙を使ったりしなければならない。
「看護婦」を表すKrankenschwesterのSchwester「姉妹」はBruder「兄弟」という対立する概念を持つが、男性の看護士をKrankenbruderとは言わない。「世話する人」という意味のPfleger(「世話する」の動詞語幹+動作主を表す派生辞)を組み合わせてKrankenpflegerと言われている。そして今では、それに-inを付けてKrankenpflegerinという女性形が使われているのである。このように、ことばの営みは堂々巡りを繰り返すようだ。
日本語で「看護婦」「助産婦」を「看護師」「助産師」と、比較的簡単に言い換えることができたのは、漢語の造語力が生産的に働いたと考えてもいいだろうか。
日本語の名詞に女性形を表す文法的な制約はなく、そもそも日本語のほとんどの名詞はいわばジェンダーフリーなのであるが、付加的に女性を表す複合語がある。婦人警官、女流作家、女社長、女医・・・という言い方は、警官や作家や社長や医者は男の職業だという前提のもとに生まれた言い方であった。普通でないから、「女」を付けて複合語にすることで、ことさらに表現するのは、有標性について上で述べたとおりである。筆者が物心ついた頃、「テレビ」は白黒だった。それがいつか「カラーテレビ」が出回るようになり、今日、テレビを「カラーテレビ」と呼ぶ人はいない。田山花袋が小説『女教師』を著した頃から比べて、教育職は女性が最も進出している分野の一つとなり、現代では「女」をつけないほうが普通だろう。つまり、女性が教師になることは、テレビがカラーであることのように「無標」になりつつあるということだ。
ある歴史学者によると、ある時代の新聞にバナナの広告が多く出回っていた頃は、人々はバナナをたくさん食べていたのだろうと考えやすいが、実は新聞広告が多いということは消費が多いことのエビデンスではなく、むしろバナナが珍しく、普通の人の暮らしにはまだなかったので、広告の多さが目立ったということだ。実際にバナナが安く普及してからはバナナの広告は無くなっていく。
女性活躍という言葉が飛び交っている間は、我が国はまだ女性が活躍できていないということか。
写真は、ドイツの助産師(männliche Hebamme) Tobias Richterさん。日本で助産師になれるのは女性に限られている。
https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/berlin-buch/unser-haus/karriere/pflegeinterview-tobias-richter/
-
- 2021年04月02日 『『言語のダイバーシティ』』
-
6回にわたり、若者ことばについての興味深い連載を続けてくださった尾谷先生、ありがとうございました。4月からは法政大学文学部日本語文学科https://www.hosei.ac.jp/bungaku/gakka/japanese/
の科長さんとしてさらに多忙な毎日を過ごされることになります。東京都心、市ヶ谷にある文学部のキャンパスは外堀沿いの満開のさくら並木が見渡せるおしゃれな立地。お時間を作って連載の内容を展開させ、当社で本にしてくださいね。若者ことばに関する投稿などは、ひきつづき尾谷昌則氏のTwitter尾谷昌則@masanori_odaniへお願いします。
さて4月6日からは仁科陽江先生による新連載が始まります。連載タイトルは『言語のダイバーシティ』初回は、ドイツでの文法上の性の言いかえの潮流など興味深い事例を紹介する「ジェンダーと言語」になります。仁科先生はドイツのErfurt大学で言語学の博士号を取得後、長年にわたりドイツで言語学教育、日本語教育に従事し、帰国され広島大学教授ポストに就かれました。専門は一般言語学、言語類型論、日本語教育など多岐にわたります。