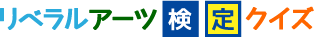言語学者が行く世界の街歩き: インド・コルカタ(ことば文化特設サイト)
ことば文化に関する気になるトピックを短期連載で紹介していきます。
-
- 2025年12月30日 『3月からの新連載のお知らせ』
-
11月から4回にわたり、ネパール、中国、エチオピア、パプアニューギニアでのフィールドワーク体験をフレッシュに綴ってくださった連載「はじめてのフィールドワーク」はいかがでしたでしょうか。執筆者のみなさま、ありがとうございました。
さて、次回は東京外国語大学世界言語社会教育センター講師/東京大学大学院人文社会系研究科の石川さくらさんによる4回の連載「言語学者が行く世界の街歩き:インド・コルカタ」が、3月より始まります。コルカタの街歩きを手がかりに、その街で用いられている言語、とりわけベンガル語のしくみや特徴を描き出されるとのことです。インド初のコルカタメトロの駅名からベンガル語の音韻と文字の仕組みを読み解いたり、市民の足であるバスの座席にまつわる暗黙のルールから人や物のカテゴリー化のあり方を考えたり、道端の喧嘩に見える重複などの文法的特徴に迫ったりと、街の風景と言語がつながる視点をお届けできるとのことですので、ご期待ください。
なお、1月・2月は休載となります。どうぞご了承ください。(野口)