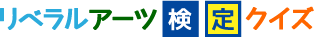インタビュー(kotoba news)
kotobaに関する気になるトピックを短期連載で紹介していきます。
-
- 2023年05月23日 『『jsPsychによるオンライン音声実験レシピ』 座談会』
-
ふ:黄、き:岸山、の:野口
の:6月に「jsPsychによるオンライン音声実験レシピ」が出版予定ですが、今日は著者兼編集者の野口が進行役になって座談会を開催したいと思います。まず、オンライン実験は、従来のオフライン実験とはどのように異なるのか説明してもらえますか?
ふ:オンライン実験は、被験者が自宅などの場所で実験に参加し、研究者は遠隔で実験を操作することができます。つまり、実験を行うための物理的な場所や機材を必要としない点が大きな違いです。
の:そうですね。地理的な制限や時間の制約などを受けずに実験ができますよね。
ふ:従来のオフライン実験と比較して、オンライン実験では被験者の負担が軽減されることもあります。たとえば、被験者が遠くの研究施設に足を運ぶ必要がないため、交通費や時間を節約することができます。さらに、被験者は自分の慣れ親しんだ環境で実験に参加することができるので、より自然な状況下での行動を観察することが可能ですね。
き:それに加えて、オンライン実験に参加する被験者の数も、従来の実験よりも多くなる傾向にあります。つまり、より多くのデータを収集することができるという利点もあるんです。
の:便利ですよね。オンライン実験に参加するのに予備知識やスキルが不要なのも大きいですね。
ふ:基本的には、パソコンを操作することができれば問題ないですからね。
き:実験者側にも従来のオフライン実験よりも費用がかからないというメリットがあります。特別な機材や設備を用意する必要がないため、実験費用を抑えることができます。
の:それもいいですね。実験者側も機材としてはパソコンを持っているだけで十分ですからね。
ふ:はい、基本的にはパソコンがあれば実験ができます。また、本の中でも紹介されていますが、オンライン実験に参加するためのソフトウェアやアプリも、ほとんどが無料で提供されています。ですので、特別な費用をかけることなく実験をおこなうことができます。
き:ただし、プログラミングの知識が必要な場合もあるため、初心者の方は苦戦することもあるかもしれません。しかし、このオンライン実験に関する書籍は、プログラミング初心者の方でも理解できるように、基本的なプログラミングの知識から解説しています。
の:実験に必要な費用もほとんどかからないし、パソコンがあればできるというのは、とても魅力的ですね。今度、レンタルサーバーを使って、規模の大きな実験をより安価に実施しようと思っています。
-
- 2023年02月21日 『連載「自然言語と人工言語のはざまで」投稿者へのインタビューその1』
-
(ゆ:は当社社長、の:は投稿者です。)
ゆ:連載も後半に入り、6月の新書化に向けて、土台作りに余念がないころと思われます。そこで野口さんが7大学18コマの非常勤勤務から、春休みというつかの間の余暇に入られたこの時期に、インタビューを試みたいと思います。
ゆ:今回の連載は英語にしろ、日本語にしろ「言語」という誰もがよく知っている身近な題材を使ってプログラミングの基礎を学ぶ、というところに価値がありそうですね。
の:ええ、カリキュラムありきでアニメーションを動かす「ゲーム」のような「教材」からスタートすることには実は疑問を抱いています。あくまで自分の経験ですが、最初に本物に触れるのが大事な気がします。練習のためにレベルを落とすのはいいのですが、最初にひとまずのゴールが見えて、カリキュラムだからやるではなくて何かをできるようになりたくて学ぶという環境があるのがポイントだと思います。
ゆ:現在はプラットフォームが使いやすくなっているという時(とき)の利もありますね。コンピュータには何度やり直しても文句をいわれないし、今回の連載では無料で使えるGoogle Colaboratoryにログインすると野口さんがコードを打ち込んだシートを用意してくれているという親切さで、私でも機械相手に「やってる~」感が味わえます。
の:ええ、私が学部生のころはテキストエディタでプログラムを書いて、変更するたびに真っ黒なコマンドラインから実行する必要があったので、エラーが出るたびにうんざりしていました。
ゆ:便利になったとはいえ、簡単なところでつまずいてしまうこともありますね。自動車は比較的簡単に運転することができますが、故障したときに自分で修理しようとすると大変でしょう。プログラミングの場合にもエラーが出た場合は困りますよね。
の:そうなんです。それでもColaboratoryなどのプラットフォームでは、変数に何が入っているかを一覧で教えてくれます。テキストエディタで書いていた時代には、変数の値や型をプリントして確かめる必要がありました。
ゆ:野口さんはプログラムを自由に書けるようになるまで何年くらいかかりましたか。
の:プログラミングを集中的に学んでいたわけではないので、ある程度書きたいものが書けるようになるまで数年かかりました。ピアノやバイオリンだとすぐに弾けるようにならなくても当然だと思ってもらえるのですが、英語やプログラミングだとそうではない(すぐにできるようになる方法が存在する)と思われているのが不思議です。
ゆ:この連載を読んで、手を動かして野口さんが用意したコードをコピペするだけでも、まったく新しい「道具」を手にしている感覚が味わえます。新しい道具であり、そのつくられ方も大勢の人が参加するなど、従来の工業製品とは違う点があるようですね。
の:そうですね。必要なものは大抵フリーでウェブ上に公開されていますし、Pythonなどの人気の言語はライブラリーなども充実しています。初めから書かなくても、すでによく使われる手続きは短いコードで実装できるようになっています。
ゆ:作られ方から派生する部分もあると思われますが、スタイルとか独特の言い回しや作法にはこういう連載や新書で慣れておくと敷居が低くなると思います。「道具」がどのような成り立ちでできているのか、連載を読むとほんの少しですが、わかったような気がします。
ゆ:野口さんの専攻は言語学ですよね。「少なくとももうしばらくのあいだは、人間はコミュニケーションに言語を使いつづけるでしょうから、根本的に言語が人間の手を離れることはないように思われます。」と述べておられますが、言語学の未来についてはどうでしょうか。
の:デジタル・ヒューマニティーズの一分野として盛んに研究が進むのではないでしょうか。これまでいわゆる文系の方法でしか分析できなかった言語を、数理的に取り扱うことができるようになってきました。しばらくの間は分析に必要なデータの整備が必要だとは思いますが。
ゆ:言語学もテクノロジーの進化を利用していかなくてはならないということでしょうか。連載の後半が楽しみですね。それではまたゴールデンウィークのころに今度は新書化や実験音声学の新書についてもお話を伺えれば、と思います。