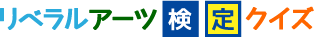《第53問》
『ロミオとジュリエット』で、リチャード・エドワーズ(Richard Edwards, 1523-66)の詩を歌詞とするソングが使用されているのは次のどの場面か?
正解
不正解
- 第一幕第五場
- 第二幕第二場
- 第四幕第五場
- 第一幕第五場
- 第二幕第二場
- 第四幕第五場
- 解説
-
現代の舞台や映画がそうするように、第一幕第五場(出逢いのシーン)や第二幕第二場(バルコニー・シーン)でも音楽が使用されていたかもしれないが、決定的な根拠はない。他方、第四幕第五場には楽師が登場し、しかも道化が歌うことを示唆するト書きがあるので、この場面が音楽で飾られていたことがはっきり分かる。
より詳しい解説を読む
この場面で道化が唄うソングの一曲が、リチャード・エドワーズの詩集(The Paradise of Daintie Deuises, 1576)にみえる「音楽への賛辞」('In commendation of Musick')という詩の一節である。また、この唄の節は、有村祐輔・吉田正俊著『シェイクスピアの音楽』(大修館、1985年刊)で参照することができる。第四幕第五場にみえる「深い嘆きに胸痛み/悲しい歌に心沈み」(松岡訳)で始まるその歌は、エドワーズのテクストではこう続く。
けれど、たちまち、音楽は、白銀の音で心を癒す
どんな悩みに苦しむ人も、甘い調べで癒される
嬉しいときには喜びが増し、悲しいときには心を励まし、
甘い調べの技により、悩める心は解き放たれる
さらに一言加えれば、唄は五感を僕とする
(以下省略)
*以上は拙訳。原文はL. E. Rollins, ed., The Paradise of Dainty Devices,
Cambridge [MA]: Harvard UP, 1923, p. 55 にみえる。悲劇的モードと喜劇的モードが混じり合うこの場面に、はたしてこの音楽がどのような意味を付与していたのか、それは分からない。大修館シェイクスピア双書『ロミオとジュリエット』の編者である岩崎宗治は、この場面に付した後注で、医者がリアを狂気から取り戻すのに音楽を使用していることにふれたうえで、「音楽は、シェイクスピアでは調和と秩序の象徴」であるといい、また、「白銀の音」(silver sound)という英語が、バルコニー・シーンで二度使用されている 'silver' (2.2.108 と165)と呼応して主題の展開と係っているかもしれないというハーリー・レヴィン(Harry Levin, 1912-94)の説を紹介しているが、(シェイクスピアでは多くの場合そうであるように)曲と主題との関係は曖昧である。
一方、シェイクスピアの芝居における音楽について、しばしばある興味深い事実が存在することが分かっている。それは「一つの場面に作用する感情のバランスを変化させ、また登場人物の心の状態を変えることさえある」(Ros King, Shakespeare: A Beginner’s Guide, Oxford: Oneworld, 2011, p. 133)というものである。この事実を示す例として、ロス・キングはシェイクスピア作品の次の二つ場面を挙げている。一つは、『オセロー』の第二幕第三場でイアゴーが「乾杯」と「スティーヴン王」の唄 ― この二曲はいずれも酒盛りの唄 ― を続けて歌う場面である。テクストでは、この唄の直後に泥酔状態で話すキャッシオーの様子は、唄の直前の様子とは極端に違って見えてしまうが、このとき観客の側に生じる情緒のバランスがイアゴーの唄 ― テクストにはその一部しか印字されていないが、この曲は、実際は、もっと長い ― によって支配されると考えれば、キャッシオーのこの「急変」は劇場では受け入れ難いものではない。もう一つの例は、『テンペスト』の第一幕第二場でエアリアルが唄を歌い、ファーディナンドがその心情の変化を露にする場面である。「汝の父は五尋も沈み」と始まるエアリアルの唄は「亡骸は今や珊瑚礁/眼(まなこ)は二つの真珠に変わり . . . 」という具合に、「暗」から「明」へと展開してゆく。この唄の醸し出す情緒こそ、父を亡くした(と少なくともこの時点ではそう信じる)深い悲しみが一目惚れへと変わるファーディナンドの変化を、劇場の観客に抵抗なく受け入れさせるドラマツルギーとして機能する、とキングは指摘する。
『ロミオとジュリエット』第四幕第五場で歌われる「音楽への賛辞」についても、おそらく同様のことが言える。ジュリエットが亡くなった(と信じる)楽師たちが、「絶えて金貨にはありつけない」という思いから心沈める場面で、道化がこの唄を歌う(そして楽師たちもそれに参加すると思われる)。テクストでは、この場面の締め台詞は、一人の楽師によって語られるこのような言葉だ ――「さあ、奥へ行こう、弔問客が来るまで/待てば、ご馳走にありつける」。落胆から希望へ、つまり「暗」から「明」へと、一八〇度変化してゆく登場人物の情緒をここでも音楽が支配し、同時に、その変化を示唆しているといえる。また、このシーンで観客の側に生じる情緒のバランスが、最終幕で起こる痛ましい事件の衝撃を緩衝するのかもしれない。